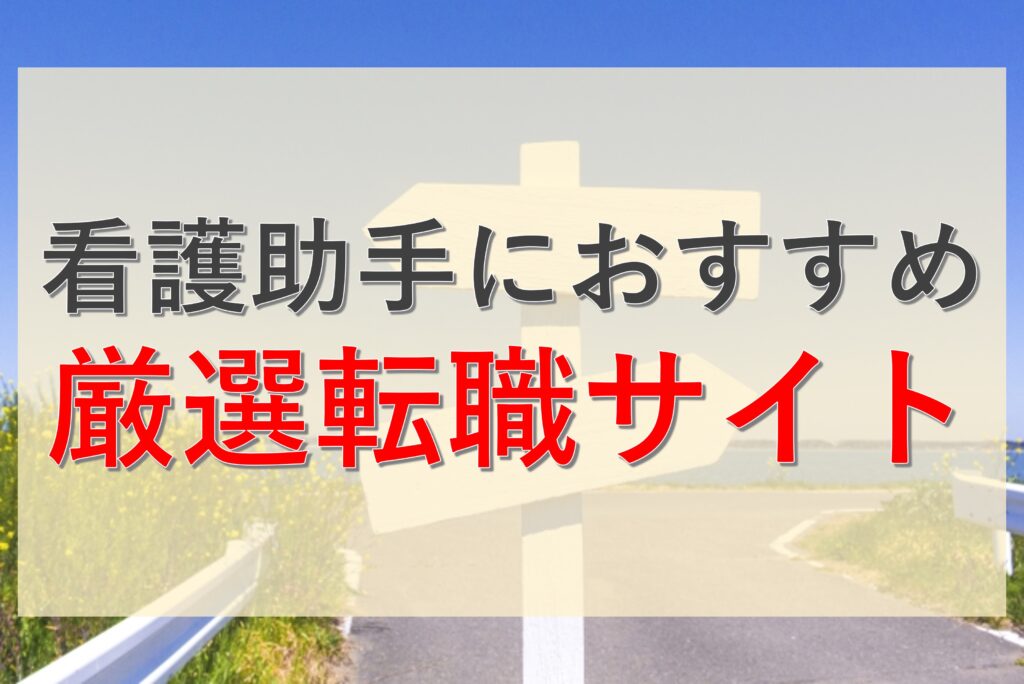
看護助手におすすめの転職サイトや派遣会社を徹底解説!

看護助手の離職率を下げるためにもっとも重要なのは、職場環境と人間関係の改善です。
本記事では、看護助手が直面しがちな身体的な負担や精神的ストレス、キャリアへの不安といった課題に対して、現場で実践できる具体的な7つの対策を紹介します。
さらに、看護助手の離職率が高い背景には何があるのか、最新の統計データをもとに、人材不足の実態とその要因も読み解いていきます。
看護助手向けおすすめサービス
看護助手の仕事探しは、
医療業界に強い転職サイトがおすすめ!
\正社員の仕事探しにおすすめ!/
\高時給の派遣求人探しにおすすめ/
「看護助手になるべきか悩む」
「今の仕事を続けることに不安がある」
こんな風に、キャリアの方向性や今の仕事に悩みやモヤモヤを抱えている人は、「キャリアバディ」をご活用ください。
キャリアコンサルタント(国家資格)保有者をはじめ、キャリア・転職のプロに相談ができるため、転職の方向性を明確にすることが可能です。
面接対策などの依頼も出来るため、「働きたい病院に採用されない」と悩んでいる人も、お気軽にご利用ください。


看護助手の人材不足の背景にある離職率の高さについて、最新の統計データを交えながら詳しく解説します。
看護助手の離職率は、他の医療・介護職と比較してどのような状況にあるのか、特に正規雇用と非正規雇用でどのような違いが見られるのかを明らかにしていきましょう。
看護助手の離職率には雇用形態によって大きな差があり、非正規雇用の看護助手は、正規雇用者に比べて著しく離職率が高い傾向があります。
日本看護協会が公表した「2024年度病院看護実態調査報告書」によると、正規雇用の看護補助者の離職率は13.7% であるのに対し、非正規雇用では26.1% と、約2倍の水準に達しています。
| 雇用形態 | 全体の離職率(※1) | 新規採用者の離職率(※2) |
|---|---|---|
| 正規雇用 | 13.7% | 24.0% |
| 非正規雇用 | 26.1% | 34.7% |
この背景には、非正規雇用による雇用の不安定さ、賃金や福利厚生などの待遇面の格差、組織への帰属意識を持ちにくいことなどが影響していると考えられます。
また、新規採用者に限ると、正規雇用者の1年以内の離職率は24.0%、非正規では34.7% にものぼり、約3〜4人に1人が年度内に職場を離れていることが分かります。
単に雇用形態だけを見るのではなく、働き続けられる環境が整っているかどうか、制度やサポート体制を確認することが、長く安心して働くためのカギとなります。
国家資格が必要な看護師と比べると、看護助手の離職率は高い傾向にあります。
前述したように、特に新規採用者の定着率には課題があり、早期離職が深刻な問題となっています。
看護助手は、看護師と連携して患者ケアを支える重要な役割を担っていますが、資格要件がないために専門性が評価されにくく、待遇面でも差が生じやすい状況です。
また、業務範囲が多岐にわたり、身体的・精神的負担が大きくなりがちなことに加え、キャリアパスの不明確さも離職の一因となっています。
以下のデータからもわかるように、看護師と比較しても看護助手の早期離職率は際立って高い状況です。
| 職種 | 年間離職率 | 新規採用者の 年度内離職率 |
|---|---|---|
| 看護補助者 (正規雇用) | 13.7% | 24.0% |
| 看護職員 (正規雇用) | 11.3% | 8.8% |
このことから、看護助手は資格要件が無く「無資格・未経験」でも始められる職種である反面、離職率が高く、決して働きやすい環境とは言えないことが分かります。
そのため、看護助手として長く働くためには、看護師との役割分担や連携のあり方を理解し、自身の将来像や働き方を明確にしておくことが非常に重要になります。
また、雇用主側にも、職場定着を支援する体制やキャリア形成の支援が求められている業界といえるでしょう。

看護助手の離職率は、同じく介護現場で重要な役割を担う介護職員と比較しても高く、特に非正規雇用者や新規採用者において高い傾向があります(以下表を参照)。
| 職種 | 雇用形態 | 年間離職率 (2023年度) |
|---|---|---|
| 看護助手 | 正規雇用 | 13.7% |
| 非正規雇用 | 26.1% | |
| 介護職 | 雇用形態問わず | 13.1% |
看護助手は、医療機関という専門的な環境の中で、看護師との連携や補助業務を担うため、介護職員とは異なる業務内容・スキルが求められます。
一方、介護職は介護施設や在宅現場での支援が主であり、キャリアパスや給与水準の仕組みも異なることが、離職率の差につながっていると考えられます。

看護助手の方が職場を離れると、医療機関や現場スタッフにさまざまな影響が生じます。
この章では、離職によって発生するコストや人的負担に焦点を当て、医療現場が受ける影響を、以下の2つのポイントについて解説していきます。
看護助手の離職が続くと、新たなスタッフの採用から育成までに多くの時間と費用がかかり、医療機関にとっては大きな負担となります。
特に、採用したばかりの人がすぐに辞めてしまうと、求人広告費や紹介手数料だけでなく、新人研修にかけた人件費までもが無駄になってしまいます。
採用に関わる代表的なコストには、以下のようなものがあります。
| 採用関連コスト | 具体例 |
|---|---|
| 求人広告費 | 求人サイトや求人誌への掲載料 |
| 人材紹介手数料 | 人材紹介会社経由で採用した場合の成功報酬 |
| 採用担当者の人件費 | 募集から面接、採用手続きまでにかかる担当者の時間コスト |
また、新人を育成する過程でも、表には見えにくいコストが発生します。
新人研修の準備やOJT(職場内訓練)期間中は、指導担当者が通常業務から一時的に離れる必要があり、現場全体に負担がかかります。
本来であれば、これらの時間と資源は患者ケアの質向上や業務改善に使えた可能性があることを考えると、離職による影響は直接的な費用負担にとどまらず、「機会損失」も大きいといえるでしょう。
看護助手が一人職場を離れると、その業務は他のスタッフが分担して担う必要があり、1人あたりの仕事量が増加します。
医療現場ではただでさえ日々忙しく業務をこなしているため、さらに業務負担が増えることで、看護助手や看護師の心身への負担が大きくなるでしょう。
たとえ新しいスタッフが入職しても、すぐに戦力となるわけではありません。慣れるまでの間は先輩スタッフが指導に時間を割く必要があり、その分さらに現場が忙しくなってしまうという現実もあります。
このような状況が続くと、休憩時間が十分に取れない、残業が常態化するといった身体的負担に加え、精神的な疲弊やモチベーションの低下といった問題も深刻化していきます。
以下は、離職によって現場スタッフに生じる主な負担とその具体例です。
| 負担の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的負担 | 残業時間の増加 休憩時間の短縮 休日出勤の発生 |
| 精神的負担 | 慢性的な人手不足への不安 同僚の離職による孤独感 業務へのプレッシャーの増加 |
| モチベーション低下 | 「頑張っても報われない」という徒労感 仕事への意欲減退 職場全体の士気低下 |
こうした負担は、仕事へのやりがいを感じにくくする原因にもなります。
「また人が辞めてしまった」「自分もいつまで続けられるだろうか」という不安が広がると、職場の雰囲気も暗くなり、さらなる離職者を生む悪循環に陥ることもあります。
看護助手の離職につながる主な5つの要因は以下の通りです。
これらの要因を一つひとつ丁寧に見ていくことで、現場で起きている課題が見えてきます。
看護助手の仕事は、患者の日常生活を支えるうえで不可欠な存在ですが、その業務内容は多岐にわたり、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。
例えば、患者の移動・入浴・排泄の介助といった直接的な身体介護は、腰痛や体力的な疲労の原因になりやすく、特に中腰姿勢や持ち上げ動作が続く現場では慢性的な痛みに悩む人も少なくありません。
さらに、夜勤を含む不規則な勤務は生活リズムを崩し、睡眠不足や健康不良を引き起こすリスクもあります。
加えて、清掃や汚物処理といった業務には、精神的なストレスを感じる人も多いのが現状です。
「看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査研究」では、「病院で働くことの難しさ」として以下が挙げられており、仕事内容そのものの大変さがうかがえます。
看護助手の仕事は体力勝負であり、精神面でもプレッシャーの大きい職種といえるでしょう。

看護助手として働くうえで、職場内の人間関係は非常に大きな影響力を持つ要素です。
特に看護師との連携は業務を円滑に進めるために欠かせませんが、コミュニケーション不足や高圧的な態度、場合によってはハラスメントなどが原因となり、強いストレスを感じてしまうケースもあります。
看護助手は看護師の指示のもとで動くことが多いため、指示の出し方ひとつで業務のしやすさが大きく変わってくるのが現実です。
例えば、指示が曖昧だったり、頻繁に変更されたりすると、どう動けばよいかわからず、業務への不安や焦りが募ることになるでしょう。
看護助手は、患者の日常生活を支えるうえで欠かせない役割を担っています。しかし、その給与水準や待遇が「業務内容に見合っていない」と感じる人も少なくありません。
看護助手の給与・年収は看護師や介護職と比べても低く(以下表を参照)、結果的に退職や採用の困難さにつながっています。
| 職種 | 給与(月額) | ボーナス | 年収 |
|---|---|---|---|
| 看護助手 | 222,500円 | 513,600円 | 3,183,600円 |
| 看護師 | 352,100円 | 856,500円 | 5,081,700円 |
| 准看護師 | 284,200円 | 622,200円 | 4,032,600円 |
| 介護職 | 282,400円 | 621,400円 | 4,010,200円 |
上表を見ると分かるように、業務内容が近い介護職と比べても給与が低いことが分かります。このような給与相場において、特に以下のような病院では、看護助手の不満が募りやすくなります。
実際に厚生労働省の調査でも、「看護補助者の確保が困難な理由」として「給与が低い」を上げた管理者は78.7%に上り、離職の直接的な原因と認識されていることが分かります。
参照:厚生労働省「看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査研究」
正社員として勤務していても、給与や待遇に不満を抱えていると離職へとつながりやすくなるため、病院側としては少しでも早く待遇改善をすることが必要になります。

看護助手の仕事は、未経験・無資格からでも始められますが、十分な教育やサポート体制が整っていない職場では、早期離職のリスクが高まる傾向があります。
業務内容は、患者の身の回りのケアから、医療器材の準備、病室の環境整備まで幅広く、一つひとつ丁寧に学ぶことが必要です。
しかし、現場が慢性的な人手不足であると、先輩スタッフも自分の業務に追われ、新人が質問する余裕すらないケースも珍しくありません。
「見て覚えて」という昔ながらの指導方法では、新人は何から始めればいいのか分からず、不安ばかりが募ってしまい、結果的に早期離職につながることがあります。
「患者さんの役に立ちたい」「医療現場で人のために働きたい」といった前向きな気持ちで看護助手の仕事を選んだのに、実際の業務とのギャップに戸惑い、やりがいを感じられなくなってしまう人も少なくありません。
看護助手の仕事は、患者の身の回りのお世話や病室の環境整備などが中心で、直接医療行為を行うことはありません。
そのため、入職前にイメージしていた「患者さんと深く関わる仕事」や「専門的なスキルを活かす仕事」とは違い、「思っていた仕事と違った」と失望してしまい、離職につながるケースもあります。
看護助手の定着率が向上することによって、医療機関の経営には様々なメリットがあります。
特に、以下の4つのポイントは、経営視点から見ても大きな効果が期待できます。
定着率の向上は、人手不足の解消だけにとどまらず、医療サービスの質の向上と経営の安定化にも直結します。
上記について、詳しく解説していきます。
看護助手の定着率が向上することは、医療機関にとって採用・研修にかかるコストを大幅に削減し、経営効率を高める重要な要素です。
看護助手を1人採用するには、求人広告の掲載費用や人材紹介会社への手数料、面接対応にかかる職員の時間的コストなど、多くの手間と費用が必要です。
採用後には、数週間から数ヶ月に及ぶ初期研修が必要で、その間には指導にあたる先輩職員の人件費や、研修資料の準備などの隠れたコストも発生します。
こうした採用・研修にかかるコストは、採用したスタッフが短期間で退職してしまった場合、すべてが無駄になってしまうというリスクを抱えています。
その上、再び同じ採用・育成のプロセスを一からやり直さなければならず、現場の負担は増える一方です。
定着率が高まれば、このような採用・研修の繰り返しを防ぎ、年間を通じた大きなコスト削減になります。これは単なる経費節減にとどまらず、教育担当者や管理者の業務負担の軽減、そして現場全体の安定感の向上にもつながります。
看護助手の定着率向上は、医療機関全体の健全な経営基盤づくりに直結する、非常に重要な効果であるといえるでしょう。
看護助手の定着率が向上することは、患者が受ける医療ケアの質と一貫性を高め、結果として患者満足度の向上に大きく貢献します。
経験を積んだ看護助手が継続的に患者ケアに関わることで、一人ひとりの状態や好み、小さな変化にも気づきやすくなり、より心のこもった、きめ細やかな対応が可能になります。
例えば、食事介助が必要な患者にとっては、いつも同じスタッフが好みや食べやすいペースを理解してサポートしてくれることが、大きな安心感につながるでしょう。
また、入浴や排泄の介助といったプライバシーに関わるケアでも、顔なじみのスタッフが対応することで、精神的なストレスが軽減されるという効果があります。
一方、スタッフが頻繁に入れ替わるような環境では、患者は不安を抱えやすくなります。
看護助手が長く勤務し、患者との間に信頼関係が築かれることで、患者は安心して療養生活を送れ、病院全体への信頼と満足感も自然と高まっていくでしょう。
さらに、患者からの「ありがとう」という言葉や笑顔は、看護助手自身のやりがいの源にもなります。
それは、スタッフのモチベーションを高め、「よりよいケアを提供しよう」という前向きな意欲を生む好循環へとつながっていきます。
看護助手の定着率が向上すると、医療機関における人材確保に良い循環が生まれます。
離職が少ない職場は、「働きやすい環境」である可能性が高く、口コミや職員の紹介を通じて自然と広まっていきます。具体的には、以下のようなポジティブな評判は、求職者にとって非常に魅力的な情報です。
あの病院は人間関係が良いらしい
新人へのフォロー体制が整っていると聞いた
看護助手の有効求人倍率は4倍を超える(※)こともあり、人材確保が難しい職種のひとつです。
※2023年度:4.13倍(参照:job tag「看護助手」)
こうした状況において、「定着率が高い=安心して働ける職場」という良い評判が広まれば、高額な求人広告を出さなくても自然と求職者が集まるようになります。
また、職員満足度が高い職場では、既存のスタッフが知人や友人を紹介するリファラル採用が生まれやすくなるのも特徴です。
リファラル採用は、採用コストを抑えられるだけでなく、職場の雰囲気や業務内容をよく理解した人材が入職してくれる可能性が高いため、ミスマッチのリスクが少なくなります。
さらに、紹介者自身も「信頼できる人と一緒に働ける」という安心感があり、既存スタッフの満足度向上にもつながるでしょう。
看護助手の定着率が向上することで、医療機関が診療報酬上の看護補助体制充実加算を算定しやすくなり、病院の収入増加に直接的に貢献する可能性があります。
この加算は、病院が質の高い看護補助体制を整備していることを評価し、一定の基準を満たすことで診療報酬が上乗せされる制度です。
この加算を算定するには、病棟ごとに以下の条件をクリアする必要があります。
看護補助体制充実加算には複数の区分があり、それぞれの要件と加算金額が異なります。
看護補助体制充実加算がとれると、毎月まとまった額の診療報酬が上乗せされるため、病院経営の安定化に直結する大きな収益源となります。
したがって、看護助手の職場環境を整え、定着率を高めることは、人件費や採用コスト削減だけでなく、病院の収益性を強化するための重要な取り組みといえるでしょう。
看護助手が安心して長く働き続けられる職場環境を実現するために、医療機関が取り組むべき7つの施策をご紹介します。
こうした取り組みを一つずつ積み重ねていくことで、看護助手が「この職場で長く働きたい」と思える環境へと改善されていくでしょう。
それでは、それぞれの施策について詳しく解説します。
看護助手の離職を防ぐためには、日々の業務の進め方を見直し、無理なく働ける環境を整えることが欠かせません。
看護助手の仕事は、患者の身の回りのケアだけでなく、病棟内の環境整備や看護師の補助など、多岐にわたる役割を担っています。
しかし、人手不足が続く医療現場では、それらを限られた時間でこなさなければならず、心身ともに大きな負担となりやすいのが現状です。
その結果、疲労やストレスが積み重なり、離職のきっかけになってしまうことも少なくありません。
だからこそ、業務のムダを省き、ICT(情報通信技術)や業務改善の工夫を取り入れて、作業効率を高めることが重要です。
業務効率化の具体策としては以下が挙げられます。
こうした取り組みによって、看護助手が本来のケア業務に専念できる環境が整い、 仕事の質の向上と離職防止の両面でプラスに働くことが期待できます。
看護助手が前向きに業務へ取り組み、「ここで長く働きたい」と思える職場をつくるために欠かせないのが、心理的安全性のある環境です。
心理的安全性とは、「自分の意見を気兼ねなく言える」「ミスを恐れず挑戦できる」といった、精神的に安心できる職場の雰囲気のことを指します。
看護助手の離職理由としてよく挙げられるのが、人間関係のストレスです。特に、看護師や他のスタッフとのコミュニケーションに関する悩みが大きな要因になっています。
こうした環境では、仕事へのモチベーションも低下しやすく、離職につながるリスクが高くなります。このような職場環境を改善するための取り組み例は以下の通りです。
| 取り組み内容 | 目的・効果 |
|---|---|
| メンター制度の導入 | 新人に対して経験豊富な先輩がマンツーマンで業務をサポートし、不安を軽減する |
| 定期面談の実施 | 上司との1対1の対話機会を設け、悩みや希望を聞き取ることで信頼関係を築く |
| チーム研修の実施 | 職種間・スタッフ間の理解を深め、協力し合う風土を育てる |
| 休憩室の環境整備 | リラックスできる空間をつくることで、心身の回復と気持ちの切り替えを促進する |
こうした施策を通じて、お互いを尊重し、支え合える文化が育まれることで心理的安全性が高まり、職場の定着率向上にもつながっていきます。
看護助手の仕事は、患者の生活を支えるうえで欠かせない大切な役割です。
その重要性や専門性、そして日々の努力に見合った給与や手当がきちんと支給されることは、仕事への満足感を高め、離職を防ぐうえでも欠かせません。
実際、看護助手の離職理由として多く聞かれるのが、「給料が仕事内容に見合っていない」という声です。
こうした業務に見合った報酬が得られないと感じたとき、仕事へのモチベーションを保つことが難しくなり、より条件の良い職場へと転職を考える要因になってしまいます。
具体的に見直すべき給与・待遇の主なポイントは以下の通りです。
| 見直す項目 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 基本給の水準 | 同地域・同規模の医療施設の給与水準を調査し、自院の給与が市場と比較して適正か確認する |
| 夜勤手当の充実 | 夜勤業務の負担に見合った手当を支給/回数に応じて加算制度を導入 |
| 資格手当の導入 | 看護助手認定実務者試験・初任者研修などを修了した職員に対するインセンティブを明確化 |
| 生活支援手当 | 住宅手当・通勤手当・家族手当など、日常生活を支える手当の整備 |
| 福利厚生の充実 | 院内保育・育児休業の取りやすさ/短時間勤務制度/制服・シューズ支給などの環境支援 |
| 昇給制度の明示 | 勤続年数や成果に応じて給与が上がる仕組みを明確化し、将来の安心感につなげる |
これらの見直しは単なる報酬改善にとどまらず、看護助手が「自分の仕事は正当に評価されている」と実感できる環境をつくることにつながります。
結果として、職員の定着率が上がり、採用コストの削減やチームの安定化、患者サービスの質向上にもつながります。


看護助手として働き始める方、特に未経験者や資格を持たない方が安心して業務に取り組むためには、充実した教育・研修制度の整備が不可欠です。
新しい環境や慣れない業務に不安を抱える中でも、基礎から丁寧に知識と技術を学べるサポート体制があれば、自信を持って患者のケアに臨むことができます。
入職直後の早期離職を防ぐとともに、長く働き続けるための土台づくりのためには、以下のような教育体制が重要です。
| 取り組み内容 | 概要・効果 |
|---|---|
| 新人研修の充実 | 病院の理念、医療安全、感染対策、個人情報保護などを座学で学び、業務の基礎をしっかり理解できるようになる。 |
| OJT(現場指導) | 先輩看護助手がマンツーマンで業務を指導。 体位変換・移乗・食事介助などを演習を交えて習得。 |
| 継続研修の実施 | 経験年数に応じたスキルアップ研修。 認知症ケア、看取り、家族対応などのテーマで専門性を高める。 |
| 資格取得支援制度 | 介護職員初任者研修や実務者研修の資格取得を支援し、キャリア形成を後押し |
教育・研修制度は、新人を支えるだけでなく、働く人自身が成長を実感し、やりがいをもって仕事に取り組むための基盤でもあります。
特に、介護職員初任者研修や実務者研修、将来的な介護福祉士資格の取得を支援する体制が整っている職場は、看護助手としての専門性を高めるうえでも非常に魅力的です。
こうしたスキルアップの道筋が明確に示されている職場は、「ここでなら長く働けそう」という安心感と、「もっと成長していける」という希望の両立を可能にします。
その結果、離職率の低下や、現場チームの安定化にもつながるでしょう。

看護助手が心身ともに健康で、長く生き生きと働き続けるためには、仕事と私生活のバランスを保てる職場環境が欠かせません。
看護助手の仕事は、夜勤や急な残業など不規則な勤務になりやすく、生活リズムが乱れやすい職種でもあります。
こうした働き方が続くと、慢性的な疲労やプライベートの充実感の欠如により、モチベーションの低下や離職の原因になることも少なくありません。
そのため、職員の定着・満足度向上を目指すためには、ワークライフバランス実現に向けた以下のような取り組みが必要になります。
| 取り組み内容 | 概要・効果 |
|---|---|
| 有休取得の促進 | 気兼ねなく休みを申請できる風土づくり。 チーム内での業務調整により連休取得のハードルを下げることを目指す。 |
| 夜勤体制の見直し | 夜勤回数の偏りをなくす、夜勤明けの翌日を必ず休みにする、夜勤中の休憩を確保するなど、過剰な負担を回避。 |
| 健康管理支援 | 夜勤前後の睡眠・食事・水分補給の工夫を周知。 セルフケア情報の提供による健康意識の向上。 |
| 短時間勤務制度の活用促進 | 育児・介護など個々のライフステージに応じて、柔軟な勤務形態を選択可能にし、継続就業を支援。 |
働きやすさは、福利厚生の枠にとどまらず、医療サービス全体の質を支える基盤でもあります。
職員が無理なく働き続けられる職場は、離職率が低く、患者への対応にもゆとりが生まれ、信頼される医療機関としての評価にもつながるでしょう。

看護助手として入職した方が、「思っていた仕事と違った」「こんなはずではなかった」と感じて早期に離職してしまうことは、現場にとって大きな損失です。
その主な原因は、採用時に十分な情報が伝えられておらず、仕事の実態と応募者の認識にギャップが生じていることにあります。
看護助手の仕事には、患者に直接貢献できるという大きなやりがいがある一方で、体力的・精神的に負担の大きい場面も少なくありません。
だからこそ、入職前に良いことだけでなく大変なことも正しく伝えることが、長期的な定着につながる第一歩になります。具体的な採用手法の改善ポイントは以下の通りです。
| 採用手法の改善例 | 詳細 |
|---|---|
| 求人情報の記載内容 | 業務のやりがいやキャリアパスに加え、「体力が必要」「立ち仕事が多い」などの負担も記載し、現実とのギャップを防ぐ。 |
| 職場見学の機会を提供 | 面接前後に病棟の雰囲気や実際の業務を見てもらうことで、職場環境への理解が深まる。 |
| 面接での対話の質 | 経歴やスキルだけでなく、仕事のイメージやストレスの対処法なども丁寧に聞き取り、相互理解を図る。 |
| 数値情報の開示 | 平均年齢・勤続年数・有給取得率など、実態に即した客観的データを開示し、安心材料とする。 |
多くの医療機関では、エージェントや人材派遣会社に採用業務を依存しがちですが、これらは1人あたりの紹介手数料が高額になりやすく、ビジネスモデル上、採用後の定着まで責任を持たないケースも少なくありません。
一方で、自院が主導して行う採用活動を強化することで、職場にマッチした人材をより低コストで、長期的に活躍してもらえる可能性が高まります。
自院での採用強化のためには、以下のような手法が効果的です。
採用時にリアルな情報を丁寧に共有し、自院に合った人材を「自ら採用する」意識を持つことが、定着率向上とコスト削減の両立につながります。
適切な採用手法を取り入れることで、教育・採用にかかる負担が軽減され、現場全体の安定化にも寄与するでしょう。
-1-150x150.png) 看護助手ラボ編集部
看護助手ラボ編集部業務の一部を人材派遣会社などに依頼する場合は、「看護助手におすすめ人材派遣会社」を参考にしましょう。
看護助手として働きたいと考えている応募者にとって、求人票の情報や面接のやり取りだけでは、職場の雰囲気や業務内容を具体的にイメージするのは難しいものです。
そのため、入職を決める前に職場見学の機会を設けることは、入職後のミスマッチを防ぎ、定着率を高めるために非常に有効な方法です。
職場見学では、以下のような情報を応募者に提供できます。
また、職場見学の際には、現在働いている看護助手と直接質問できる時間を設けることをおすすめします。
仕事のやりがいや大変さ、職場の人間関係、新人へのサポート体制などを実際に質問することで、入職後の働き方をより具体的にイメージできるようになるでしょう。
医療機関も、良い点だけでなく、現在抱えている課題や改善に向けた取り組みを正直に伝えることで、応募者との信頼関係を築くきっかけになるため、おすすめの施策といえます。
看護助手がやりがいを持って働き続けられる職場環境とはどのようなものか、特に大切な以下4つのポイントに絞って詳しく解説します。
それぞれ詳しく解説していきます。
看護助手の仕事は、患者の身の回りのお世話や介助、病室の環境整備、医療器具の準備・片付けなど、幅広い業務を担う重要な役割です。
これらを円滑に行うには、看護師をはじめとする他の医療スタッフとの連携が欠かせません。
良好な人間関係が築かれている職場では、スタッフ同士がお互いを尊重し合い、自然と協力しやすい雰囲気が生まれます。
こうした環境は、看護助手のモチベーション向上やストレスの軽減につながり、離職率の低下にも寄与します。
看護助手の仕事は、身体介助など体力的な負担が大きい業務も多く含まれるため、毎月の給与だけでなく、福利厚生の充実度も働きやすさを左右する重要なポイントです。
例えば、住宅手当や家族手当、通勤手当は、日々の生活を安定させる強い味方になります。また、職員食堂の食事補助や、売店の割引利用なども、嬉しい福利厚生となるでしょう。
さらに重要なのは、育児休暇や介護休暇、看護休暇といった制度が整っているだけでなく、実際にそれらの休暇を取りやすい雰囲気があるかどうかです。
結婚や出産、家族の介護など、人生の大きな節目に柔軟に対応できる環境が整っていれば、看護助手として安心して長く働き続けることができます。
福利厚生の充実は、職員を大切にする職場の姿勢の表れともいえるでしょう。
看護助手の勤務体制は、日勤だけでなく、早番・遅番・夜勤などのシフト勤務が一般的です。こうした勤務形態は、時に生活リズムを乱しやすく、心身への負担が大きくなることもあります。
だからこそ、個々のライフスタイルや事情に応じて、勤務時間や曜日、勤務日数を柔軟に調整できる環境がある職場は、無理なく長く働き続けるうえで非常に魅力的です。
例えば、育児中の方や家族の介護をされている方にとっては、短時間勤務制度やパートタイムでの勤務、特定の曜日を固定で休めるといった選択肢があると、仕事と家庭の両立が格段にしやすくなります。
また、残業が少なく、定時で退勤できる日が多い職場であれば、プライベートの時間を計画的に確保できるため、心身のリフレッシュや自己啓発に取り組む余裕も生まれます。
勤務形態の柔軟性は、看護助手の定着率を高め、多様な人材が活躍できる職場環境を作るための重要な要素です。
看護助手として長く働き続けるには、日々の業務を通じて知識や技術を高められる環境が欠かせません。
職場に段階的な研修制度があったり、外部研修への参加を積極的に支援してくれる体制が整っていたりすると、働きながら無理なくスキルを磨くことができます。
さらに、介護福祉士実務者研修や、介護職員初任者研修などの資格取得を支援する制度があれば、明確な目標を持って専門性を高められるでしょう。
また、将来的なキャリアパスの選択肢が用意されているかどうかも、長く働くうえで重要な要素です。
たとえば、看護助手であってもチームリーダーや副主任といった役職を任される制度があれば、責任ある立場を目指してキャリアを積むモチベーションにつながります。
さらに、複数の施設を展開している法人では、グループ内での異動や配属変更を可能にすることで、ライフステージや適性に合わせた働き方の選択肢を広げることも可能です。
このようなキャリア支援体制の充実は、個人の成長を後押しするだけでなく、スタッフ全体の専門性を高め、結果として職場全体の質の向上にも寄与します。




看護助手の離職率が高い背景には、業務の大変さや人間関係のストレス、待遇への不満など、さまざまな要因があります。これは、働く本人にとっても医療機関にとっても大きな課題です。
しかし、適切な対策を講じれば、この状況は十分に改善できます。重要なのは、多角的な視点から働きやすさを見直すことです。
こうした取り組みを進めることで、看護助手が安心して長く働ける職場環境が整います。
その結果、看護助手は仕事にやりがいを感じられるようになり、患者さんからの「ありがとう」という感謝の言葉に大きな喜びを見出せるようになるでしょう。
医療機関にとっても、人材の安定確保や医療サービスの質の向上といった具体的な成果が期待できます。だからこそ、看護助手が安心して働ける職場づくりこそが、離職率を改善するための最大のポイントと言えるのです。




の仕事はきつい?働くメリット・デメリットと役立つ資格を解説-300x200.jpg)
の仕事はきつい?働くメリット・デメリットと役立つ資格を解説-300x200.jpg)













