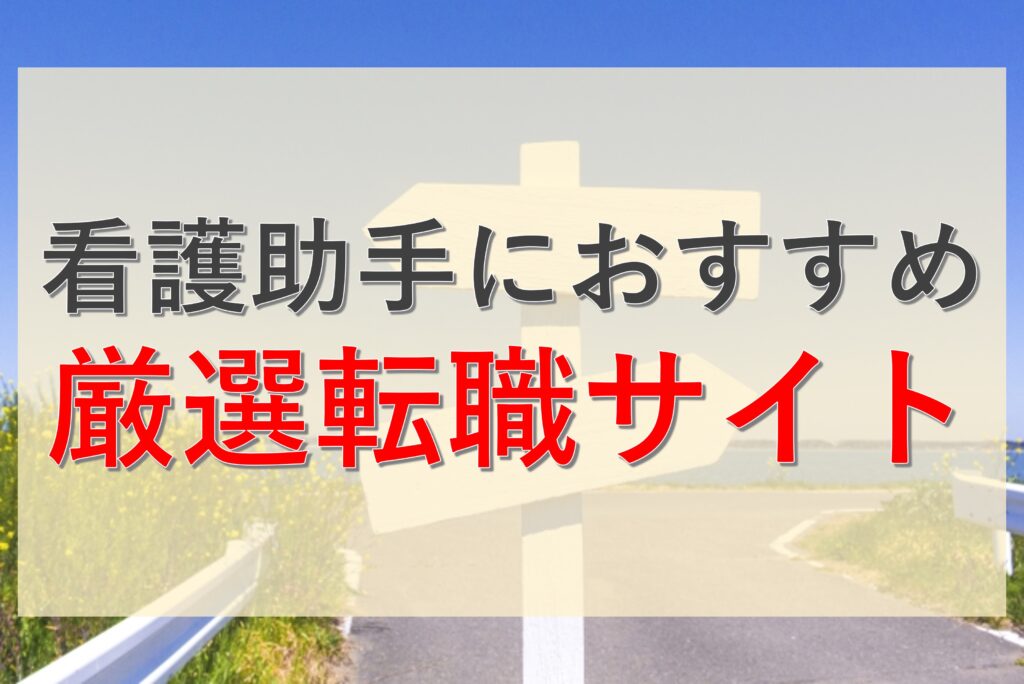
看護助手におすすめの転職サイトや派遣会社を徹底解説!

特定技能制度を活用した外国人看護助手の採用は、医療現場の人手不足を解消しつつ、質の高いケア提供を実現できる有効な選択肢です。
本記事では、特定技能「介護」で看護助手を受け入れるための要件に加え、特定技能取得者を看護助手として採用するメリットや、実際の採用方法について解説します。
医療機関と外国人材の双方が「採用してよかった」「働いてよかった」と実感できる、長期的かつ安定した雇用関係づくりに役立つ情報をお届けします。


特定技能とは、日本国内の人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
2019年4月に制度が創設され、介護分野を含む16分野が対象になっており、特定技能には以下の2つの区分があります。
| 区分 | 対象分野 | 技能レベル | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 16分野 | 一定の専門性・技能 | 1年を超えない範囲で指定された期間ごとに更新 ※通算で最長5年まで延長可能 (家族帯同は基本的に不可) |
| 特定技能2号 | 11分野 | 熟練した技能 | 3年、1年、6か月のいずれか ※通算在留期間の制限なし |
2025年5月現在、介護分野では「特定技能1号」のみ対象です。
特定技能「介護」で働く外国人は、以下のような現場の介護業務全般に従事します。
※2025年4月の制度改正により、一定の条件を満たせば訪問介護業務にも従事可能
病院で働く看護補助者の場合、上記の特定技能介護で従事可能な業務において働くことになります。

特定技能「介護」の資格を取得すれば、外国人材も日本の医療機関で看護助手(看護時補助者)として働くことができます。
特定技能制度は、介護人材不足の解消と外国人材の活躍促進の両面で有効な仕組みであり、以下のようなメリットがあります。
| 立ち位置 | メリット |
|---|---|
| 医療機関側 (雇用側) | 人材不足の解消につながる 看護助手を安定的に確保できる |
| 外国人材側 (労働者側) | 専門性(介護スキル・日本語能力)を活かせる 特定技能の期間中に「介護福祉士」を取得すれば更新回数上限無しで在留可能 |
看護助手は、患者の日常生活を支える役割を担い、以下のような業務を行います。
これらの業務は、特定技能「介護」の在留資格で認められている身体介護および付随業務と一致しており、外国人材も十分に対応可能な業務内容です。
ただし、医療行為を行うことはできず、「注射」や「点滴」「採決」等の業務は医師や看護師などの有資格者のみ認められています。
そのため、医療機関が外国人を看護助手として受け入れる際には、担当させる業務の範囲を明確にするとともに、適切な指導体制・監督体制を整備することが不可欠です。

特定技能「介護」で看護助手を受け入れるためには、外国人本人と受け入れ機関の双方が満たすべき要件があります。
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 年齢・健康条件 | 満18歳以上で健康であること |
| 介護技能評価試験 | 介護技能評価試験の合格 |
| 日本語能力試験 | JLPT N4以上 または JFT-Basic(A2相当)の合格 |
| 介護日本語評価試験 | 介護現場で必要な日本語理解を問う試験の合格 |
また、受け入れ機関(病院・介護施設)は、以下のような法令に基づいた雇用条件を整備する必要があります。
外国人材が安心して日本で生活・就労できるよう、受け入れ機関には1号特定技能外国人支援計画の実施が義務づけられています。
これらの支援業務は、受け入れ先の病院が自ら実施することも、登録支援機関へ委託することも可能です。
また、介護分野で特定技能の外国人を受け入れる場合には、厚生労働省の所管である「介護分野における特定技能協議会」への加入が義務づけられています。
介護分野における特定技能協議会への加入手続きは、在留資格の申請前までに完了しておく必要があるため、事前の準備が重要です。
特定技能「介護」を取得するためには、以下の3つの試験に合格する必要があります。
これらの試験は、外国人が日本で介護業務に従事するうえで必要な知識・技術・言語能力を評価するもので、制度上非常に重要な位置づけとなっています。
介護技能評価試験は、外国人が特定技能「介護」の在留資格を取得するために必要な試験のひとつであり、介護業務に必要な知識と実技能力を評価する重要な試験です。
介護技能評価試験の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出題内容 | 全45問 60分 学科試験:40問 介護の基本(10問) こころとからだのしくみ(6問) コミュニケーション技術(4問) 生活支援技術(20問) 実技試験:5問 判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 |
| 試験形式 | CBT方式(試験会場のパソコンで受験) |
| 合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |
また、介護技能評価試験合格率(2025年3月)は以下の通りとなっています。
| 地域 | 受験者数 | 合格者数 | 介護技能評価試験 合格率 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | 119人 | 103人 | 86.6% |
| カンボジア | 4人 | 2人 | 50.0% |
| ネパール | 39人 | 30人 | 76.9% |
| インドネシア | 321人 | 278人 | 86.6% |
| 日本(在留外国人) | 966人 | 697人 | 72.2% |
| モンゴル | 3人 | 3人 | 100.0% |
| ミャンマー | 978人 | 920人 | 94.1% |
| タイ | 22人 | 18人 | 81.8% |
| インド | 70人 | 43人 | 61.4% |
| スリランカ | 63人 | 36人 | 57.1% |
| ウズベキスタン | 5人 | 1人 | 20.0% |
| バングラデシュ | 59人 | 42人 | 71.2% |
| ベトナム | 66人 | 61人 | 92.4% |
上表を見ると分かるように、合格率は国によって差があるものの、介護技能評価試験は十分な準備をすれば多くの人が合格できる難易度といえるでしょう。
特定技能「介護」の在留資格を取得するには、一定の日本語能力があることの証明が必要です。
その評価基準となるのが、以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。
| 試験名 | 合格基準 | 合格率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT)N4 | 180点満点中90点以上 ※言語知識・読解:120点中38点以上が必要 ※聴解:60点中19点以上が必要 | 国内:36.3% 海外:35.0% (2024年12月) | 言語知識、読解、聴解の3つの要素によりコミュニケーション能力を測っている |
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | 250点満点中200点以上 | 40〜50%程度 (2024年) | 日本の生活場面でのコミュニケーションに 必要な日本語能力を測定 |
上表のどちらか一方に合格すれば、特定技能「介護」に求められる日本語能力要件を満たしたことになります。
介護分野の特定技能で求められる日本語試験は、日常生活に必要な日本語が理解できるかどうかを問うレベルであり、しっかりと対策すれば合格可能な難易度です。
ただし、介護分野の特定技能実習生として働くためには、次に紹介する「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
介護日本語評価試験は、特定技能「介護」の在留資格を取得する際に必要な試験のひとつで、介護現場で使われる日本語力を評価するための試験です。
一般的な日本語能力に加えて、介護の専門用語や、高齢者・利用者とのコミュニケーションに必要な実践的日本語スキルが求められます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | 介護現場での会話・記録・報告などに必要な日本語能力の評価 |
| 出題内容 | 全15問 30分 介護のことば(5問) 介護の会話・声かけ(5問) 介護の文書(5問) |
| 試験形式 | CBT方式(試験会場のパソコンで受験) |
| 合格基準 | 問題の総得点の73%以上 |
介護日本語評価試験は「基礎的な介護日本語を理解し、現場でスムーズにコミュニケーションが取れるかどうか」が評価されます。
介護日本語評価試験の国内受験者の合格率は74.7%(2022年度)となっており、しっかりと準備すれば、独学でも十分に合格可能な難易度であることが分かります
技能実習2号(介護分野)を良好に修了した外国人は、特定技能「介護」への移行時に必要な3つの試験がすべて免除されます。
免除される理由として、技能実習2号(介護分野)を良好に修了した外国人は、すでに日本の介護施設などでの現場経験を積み、一定の知識・スキル・日本語能力を習得しているとみなされるためです。
技能実習2号から特定技能「介護」への移行は、追加の試験が不要で、そのまま日本で働き続けられる点が大きなメリットです。
一方で、すでに技能実習生を受け入れている医療機関からは、「特定技能は転職が自由なため不安」という声も聞かれます。
それでも、慢性的な人手不足が続く看護助手の採用においては、特定技能人材は貴重な戦力となり得る存在といえるでしょう。
 山下真由美(行政書士)
山下真由美(行政書士)「良好に修了した」と認められるには、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
②実技試験に合格していなくても、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書を提出すること。
また、介護分野以外の技能実習2号を良好に修了した外国人が特定技能「介護」へ在留資格を変更する場合には、日本語能力試験は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験は必要なため、注意しておきましょう。
特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人を看護助手として採用することは、医療機関や介護施設にとって大きく分けて3つのメリットがあります。
特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人を看護助手として採用することは、慢性的な人材不足に悩む医療・介護現場にとって、有効な対策です。
実際、看護助手の有効求人倍率は4.13倍(2023年度)に達しており、求職者1人に対して4件以上の求人がある状況です。
参照:job tag「看護助手」
こうした中で特定技能「介護」人材は、入国前に取得に必要な試験に合格しているため、基礎的な知識と技能をすでに備えています。そのため、採用後すぐに基本的な介護業務を現場で担うことが可能です。
結果として、看護師や日本人スタッフの業務負担が軽減され、チーム全体の業務効率向上にもつながります。


外国人看護助手の採用は、医療・介護現場に多様性をもたらし、業務や組織運営に新たな視点や刺激を与えるきっかけとなることがあります。
実際の現場でも、以下のようなポジティブな変化が見られるケースがあります。
すべての現場で起きるわけではありませんが、多様性を受け入れる姿勢が、組織の柔軟性や風通しの良さにつながる可能性があると言えるでしょう。
特定技能制度では、外国人材が日本で安心して長く働けるよう、受け入れ機関に対して幅広いサポート体制の整備が義務づけられています。
この支援体制が、生活の安定と職場への早期適応を後押しし、結果として高い定着率の実現を見込めます。
受け入れ機関に求められる主な支援内容は、以下のとおりです。
こうした支援は、単なる福利厚生ではなく、外国人材が職場に定着するための仕組みとして機能します。
安心して働き続けられる環境を整えることが、結果的に組織全体の人材確保の安定化にもつながるのです。


医療機関や介護施設における人手不足の解消策として、特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人を看護助手として採用する動きが広がっています。
特定技能外国人の採用方法には、主に以下の3つの手段があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
特定技能外国人を看護助手として採用する際、最も現実的で再現性の高い方法が、登録支援機関の活用です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された事業者で、受け入れ期間から委託を受けて「外国人材への法定10項目」をはじめとした支援業務を担う専門機関です。
特に、はじめて外国人材を受け入れる医療機関や、外国人雇用に慣れていない施設にとっては、専門的な支援を一括で受けられる心強い存在となります。
登録支援機関を活用する主なメリットは以下のとおりです。
登録支援機関の中には、有料職業紹介の許可を受けている事業者も多く、特定技能外国人の採用支援まで一貫して対応できる点が大きな魅力です。
送り出し機関と連携しているケースでは、日本語能力や医療現場での適性を考慮したマッチングも期待できます。
ただし、登録支援機関の利用費用には明確な基準がなく、支援内容や契約期間に応じて月額費用が発生するケースが一般的です。
そのため、利用する際は支援内容とあわせて、報酬の総額や支払い条件を事前にしっかり確認しておくことが重要です。
すでに日本国内に在住している特定技能外国人を、できるだけスピーディに看護助手として採用したい場合には、転職エージェント(有料職業紹介会社)の活用が効果的です。
特に医療・介護分野に特化したエージェントは、以下のような候補者情報を豊富に保有しています。
これらの人材は、日本語能力や生活習慣への適応が進んでいることが多く、採用後の教育コストや職場定着のリスクも比較的低い点がメリットです。
なお、転職エージェントが登録支援機関ではない場合、採用後に必要な支援10項目は自院で対応する必要があります。
自院で支援体制の構築が難しい場合には、採用後に別途、登録支援機関と契約して支援業務を委託することも検討するといいでしょう。


採用コストを抑えたい、理念に合った人材を自ら選びたいと考える医療機関・介護施設にとっては、自院で直接募集を行う方法も一つの選択肢です。
登録支援機関や転職エージェントを介さないことで、紹介手数料や支援を委託するコストを削減できるというメリットがあります。
しかしその一方で、採用から支援までのすべての手続きや実務対応を自院で担う必要があるため、相応の準備と体制が求められます。
自院で直接募集する際に対応が必要になる採用・支援業務は以下の通りです。
| 必要業務 | 詳細 |
|---|---|
| 採用手続き | 求人情報の作成・掲載 選考 面接(オンライン含む) |
| 入管対応 | 海外在住者:在留資格認定証明書(COE)の申請取次 国内在住者:在留資格変更許可申請取次 |
| 支援義務 | 採用後の法定10項目の支援を自院で実施する必要あり |
| その他リソースの確保 | 多言語対応スタッフ、申請知識のインプット、現場の支援体制の構築、時間と人員の確保 |
これらの対応には、専門的な知識や経験、そして十分な人員体制の構築が欠かせません。制度の理解や各種手続き、人材支援を含めて、最初からすべてを自院のみで完結させるのは非常に難易度が高いといえます。
そのため、まずは登録支援機関など外部の専門機関のサポートを受けながら、制度に慣れていくことが重要です。
そして、一定の経験とノウハウが蓄積され、外国人材の受け入れに自信がついた段階で、段階的に直接採用へと移行していくのが現実的な進め方といえるでしょう。



海外から採用する場合は、送出し国によって取り扱いが異なります。そのため、手続きの詳細を出入国在留管理局のHPで確認する必要があります。
また、日本国内で他の在留資格から特定技能へ変更を行う場合も、外国人の出身国や元の在留資格によって必要手続きが異なる可能性もあります。
その場合は、事前に駐日大使館や地方出入国在留管理局にお問い合わせの上で、手続きを進めることをおすすめします。
特定技能の在留資格を持つ外国人を看護助手として医療・介護現場に受け入れる際の、事前に理解しておくべき重要なポイントは以下の通りです。
上記5つの視点を押さえることで、外国人材が安心して働ける環境づくりと、病院全体の安定運営につながります。
それぞれ詳しく解説していきます。
特定技能「介護」の資格で働く外国人は、あらかじめ法律で定められた範囲の仕事しか行うことができません。
これは、本人の安全を守るためでもあり、患者に安心してサービスを受けてもらうためにも大切なルールです。
特定技能「介護」で認められているのは、具体的に以下のような生活支援に関する業務です。
これらの業務はすべて、看護師や医師の指示・監督のもとで行う非医療行為です。
一方で、次のような業務は「医療行為(医行為)」とされ、無資格者が行うことは法律で禁止されています。
無資格のまま医療行為を行うと、当事者本人だけでなく、施設や病院側も法的責任を問われる可能性があります。
そのため、外国人を看護助手として採用する際には、業務範囲や禁止事項について十分な教育と指導を徹底することが不可欠です。
特定技能「介護」で看護助手として働くためには、一定レベルの日本語能力が求められます。
しかし、実際の医療・介護現場で必要な日本語力とはギャップがあることも多く、入職後のサポートが非常に重要です。
これらは、入職後の継続的な学習支援と現場経験によって定着していきます。
外国人看護助手が安心して働ける職場づくりには、日本人スタッフの協力が欠かせません。特にスタッフ間のコミュニケーションにおける「やさしい日本語」での対応は、ミスや不安の軽減に効果的です。
外国人看護助手が安心して質問・相談できる雰囲気づくりが、早期の職場適応につながります。
また、日本語力に不安のある外国人看護助手の場合には、同じ母国出身のスタッフがすでに勤務している病棟で働いてもらうことも、有効な取り組みといえるでしょう。
特定技能の在留資格で外国人看護助手を雇用する医療機関・介護施設は、外国人材が日本で安心して働き、暮らしていけるように支援する義務があります。
具体的には、住居の確保や日本語学習支援、相談体制の整備など10項目に及ぶ具体的支援が求められます。
これらの支援は、受け入れ機関が自ら実施することも、専門の登録支援機関(RSO)に委託することも可能です。
いずれの方法を選ぶ場合でも、単に支援計画を策定するだけでなく、その内容が実際に外国人看護助手にとって意味のある支援となるよう、丁寧に寄り添いながら実行していく姿勢が求められます。
特に、定期的な面談の実施は、外国人材の不安や悩みを早期に把握し、安心して長く働ける環境を整えるために必要な取り組みのひとつといえるでしょう。
特定技能の外国人看護助手が、日本の医療・介護現場でスムーズに働き、地域社会にも自然に馴染んでいくためには、地域や文化への配慮を含む環境づくりが欠かせません。
これは外国人材本人だけでなく、受け入れ側(病院・施設・地域住民)の理解と協力が重要です。日本の生活環境は、外国人にとって「知らないこと」が多く、不安や誤解の原因にもなり得ます。
特に以下のような情報は、来日前または入職直後にわかりやすく丁寧に伝えることが大切です。
| 生活習慣の例 | 配慮・サポート内容 |
|---|---|
| ゴミの分別・収集ルール | ピクトグラムや母語の説明資料を活用 |
| 夜間の音や近隣トラブル対策 | 生活音に関するマナーの事例を共有 |
| 地域の祭り・避難訓練 | 積極的な参加を促し、交流のきっかけに |
職場における文化的配慮は、働きやすさだけでなく、信頼関係の構築につながります。
「日本ではこうするのが当たり前」という前提を一度リセットし、相手の文化や価値観に柔軟に対応する姿勢が、共に働くうえでの信頼と安心感を育むことにつながるでしょう。
特定技能の資格で来日した外国人看護助手に長く安心して働いてもらうためには、さまざまな面からの支援と離職防止対策が欠かせません。
離職は単に人材を失うだけでなく、以下のような悪影響を及ぼします。
特に特定技能外国人は技能実習生と異なり、在留資格の範囲内で他施設への転職が可能です。
職場環境に満足できなければ、離職・転職という選択肢を容易にとれるため、定着率を高めるための環境づくりがより重要となります。
そのため、以下の離職につながる要因を確認し、必要な対策を講じるように心がける必要があります。
| 離職の要因 | 主な対策 |
|---|---|
| 職場環境・人間関係の問題 | メンター制度の導入(先輩スタッフが相談役となる体制) 定期的な1on1面談で悩みを早期発見 文化的背景への理解を深める研修 (異文化理解・アンコンシャスバイアス対策) |
| 給与・待遇への不満 | 日本人スタッフと同等の給与水準 福利厚生の整備 昇給や評価制度の明確化と定期的な説明 |
| 日本語能力・コミュニケーションの壁 | 「やさしい日本語」使用の啓発と実践支援 業務用語を含む日本語学習の機会提供(教材・eラーニング) 視覚支援ツール(ピクトグラム、翻訳アプリなど)の活用 |
| 労働条件・勤務環境の問題 | 夜勤、休日シフトの希望制導入や回数調整 宗教的慣習や文化に配慮した休憩 食事環境の整備 ハラスメント防止の明文化と相談窓口の周知 |
外国人看護助手を、単なる補助スタッフではなく、職場を支える大切な仲間として迎え入れる意識が、定着率の向上にもつながります。
特定技能制度を活かすには、採用して終わりではなく、継続的な育成・フォロー体制の整備が不可欠です。
中長期的な視点での人材戦略として、離職を防ぐ仕組みと職場文化の醸成に取り組みましょう。


慢性的な人手不足に悩む医療現場において、特定技能「介護」の資格を持つ外国人材を看護助手として受け入れることは、有効な人材確保策のひとつです。
特定技能制度を活用すれば、身体介護や環境整備など、看護助手の主な業務に即戦力として対応可能な人材を採用できます。採用方法は主に次の3つです。
それぞれにメリット・注意点があるため、自院の体制や目的に合った方法を選びましょう。
外国人材が「大切にされている」「成長できる」と感じられる環境づくりは、定着率の向上だけでなく、職場全体の雰囲気やサービスの質の向上にもつながります。
制度を正しく理解し、丁寧な準備と支援体制を整えることで、安定した人材確保とチーム力の強化を実現しましょう。



高齢者人口の増加と少子化の影響により、介護・医療現場の人手不足は今後さらに深刻化すると予測されています。
そんな中において、外国人の介護人材の受け入れは、その対策の一つとして現実的かつ有効な手段といえるでしょう。
外国人材の定着と質の高い介護のためには、国籍を問わず、チームの一員として共に成長し、支え合える関係を築くことが重要になります。
そのためには採用だけでなく、言語や文化への配慮、段階的な育成支援、職場内での信頼関係づくりが鍵となるでしょう。
特定技能制度を正しく理解し、長期的な視点で取り組み、安心できる介護体制の実現へつなげましょう。


【保有資格】
【経歴】
外国人の在留資格手続きに精通した申請取次行政書士として活躍するほか、著作権や相続・遺言、空き家問題など幅広い分野に対応。
行政書士・社会保険労務士の資格を活かし、「人」に関する課題解決を通じて企業経営の発展にも尽力。
東京農工大学卒業後は広報の現場を20年間経験し、2018年に行政書士として独立。
2025年7月28日監修




の仕事はきつい?働くメリット・デメリットと役立つ資格を解説-300x200.jpg)
の仕事はきつい?働くメリット・デメリットと役立つ資格を解説-300x200.jpg)













