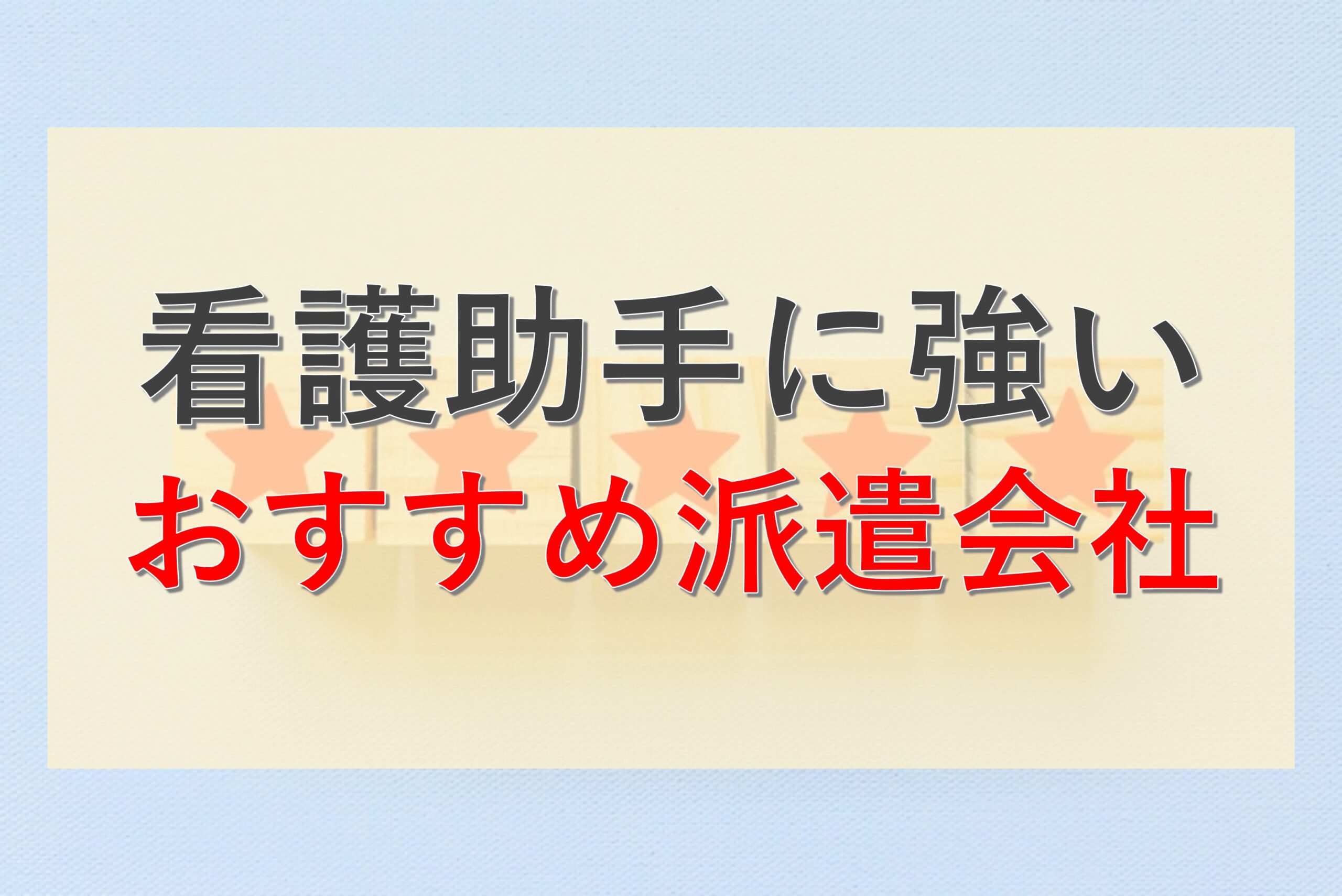
【厳選】医療事務の資格を取るならどれがいい?おすすめ資格と難易度を解説!

一般的に「医療事務」と呼ばれる資格は複数あり、どの資格を取得すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。実は医療事務の仕事は資格がなくても始められますが、資格があることで就職・転職で優位に立てたり、より高い収入を目指すことが可能です。
本記事では、資格選びで失敗しないよう、厳選したおすすめ医療事務資格の特徴や難易度、取得方法までを徹底解説します。
医療事務で働きたい人向け!
おすすめサービス
医療事務の転職なら、
医療業界に強い派遣会社に登録!
\求人数や特徴を徹底比較!/


そもそも医療事務に資格は必要なのか
医療事務の仕事を始めるにあたって、多くの方が「資格は必須なのだろうか」という疑問を持つでしょう。
結論としては、医療事務員として就職するために資格は必須ではありません。しかし、資格を持っていることで様々なメリットがあり、キャリアの可能性を大きく広げることができます。
医療事務は未経験でも働ける仕事
医療事務は、実は未経験者でも働き始めることができる職種です。
多くの医療機関では、資格や経験の有無に関わらず、人柄や意欲を重視して採用を行っています。
-1-150x150.png) 看護助手ラボ編集部
看護助手ラボ編集部医療事務の仕事は、診療報酬にかかわる会計だけではなく、基本的に受付業務を兼ねることが一般的です。
そのため、就職にあたっては事務職としての経験だけではなく、接客業の経験も活かせる仕事といえます。
採用時に資格は必須条件ではない
前述の通り、医療事務員の仕事は法的に資格は必須ではなく、実際の求人でも無資格者でも応募できるケースが多いです。
また、電話応対や来院者への適切な対応といった基本的なビジネスマナーと接遇スキルも重要な要素です。さらに、書類作成や数値処理といった正確な事務処理能力も、医療事務職には欠かせない資質として評価されています。
そのため、医療事務の資格は持っていれば有利になるものの、就職のためにはそれ以外のスキルも総合的にみられるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務の資格があれば就職・転職の幅が広がるものの、仕事に就くことが目的であれば、まずは気になる求人を探すことがオススメです。
就職優先の場合は、まずは医療事務として働きつつ、足りない知識を埋めるために資格取得を検討するといいでしょう。
現場で本当に必要なスキルとは
医療事務の現場で真に必要とされるスキルは、医療保険制度の基礎知識やレセプト作成の技術、医療用語の理解といった実務的なスキルが基本として求められます。
これに加えて、患者さんへの思いやりの心や、医療スタッフとの円滑なコミュニケーション能力、日々の業務におけるストレス管理能力といった対人スキルも非常に重要です。
これらの総合的なスキルは、実務経験を積みながら徐々に身についていくものですが、資格取得の過程で基礎知識を習得しておくことで、より早く実務に対応できるようになります。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
少しでも早く現場で活躍したい人は、就職前に医療事務の資格を取得するといいでしょう。
>医療事務のおすすめ資格は本記事のこちらで解説
医療事務の資格取得のメリット
医療事務は、病院やクリニックの運営を支える重要な職種です。医療事務の資格は必須ではありませんが、取得することで以下のメリットが得られます。
医療事務員には、医療費の計算やレセプト業務、受付対応など幅広い業務を担うため、一定の知識とスキルが求められます。
未経験でも就職しやすい分野ではありますが、資格を取得することで、上記のように転職やキャリアアップにおいて多くのメリットが得られます。
転職活動で優位に立てる
医療事務の資格を保有していると、履歴書や職務経歴書に書ける強みが増え、選考で有利に働くことが多いです。
未経験者の中でも、事務職自体の経験が無い人が医療事務にチャレンジする場合、知識の証明として資格が大きな武器になります。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務の求人は人気が高い反面、応募者数も多く競争が激しくなりがちです。
その中で他の就職希望者と差別化するためには「何ができるか」を明確に伝える必要があります。
資格は「知識やスキルの証明」として説得力があり、面接での自己PRにも繋がるので、転職成功率を高めるうえで非常に有効です。
基礎知識があるため実務をスムーズに習得できる
医療事務の資格取得の過程で学ぶ知識は、実務の場面で大いに役立ちます。
医療事務の資格取得では、医療保険制度、診療報酬の仕組み、レセプト作成のルールなど、実際の業務に直結する内容を学びます。そのため、就職後に初めて知るような専門用語や業務フローも、スムーズに理解することができます。
また、事前に医療事務ソフトやカルテの見方に触れておくことで、OJT期間の習熟度にも差が出やすくなり、現場での評価アップにもつながるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
実際の現場では、病院独自のルールや仕事の仕方に戸惑うこともありますが、医療保険における知識は病院ごとに変わることはありません。
そのため、医療事務の資格を取得することで、どんな病院に就職することになっても、実務の習得がスムーズに進むでしょう。
資格手当で収入アップが期待できる
多くの医療機関では、医療事務の資格保持者に対して資格手当を支給しています。これは基本給に上乗せされる形で支給され、月額数千円から1万円程度の収入アップにつながります。
また、資格を複数持っていることで、昇給や昇格の判断材料として評価される場合もあり、長期的な収入アップにも繋がります。
医療機関によって資格手当の金額や制度は異なりますが、長期的なキャリア形成において大きなメリットとなることは間違いありません。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療業界は専門性が重視される世界です。
実務経験に加え、給与に直結する「見えるスキル」として資格を持つことで、労働条件の交渉材料にもなるでしょう。
医療事務資格の種類
医療事務の分野には、複数の民間資格が存在しており、それぞれ学べる内容や目指せる業務の範囲が異なります。
どの資格を選ぶかによって、就職・転職活動の際のアピールポイントや、キャリア形成の方向性にも影響するため、自分の目標や現在の状況に合わせて選択することが重要です。
医療事務の資格を大きく分けると、以下の3種類に分類できます。
それぞれ詳しく解説していきます。
医療事務全般の基礎を学べる資格
未経験から医療事務の仕事を目指す方に適しているのが、医療事務の基本的な知識やスキルを広く学べる資格です。
これらの資格は比較的難易度が低く、独学や通信講座でも取得しやすいため、「まずは医療事務を学んでみたい」「未経験だけど病院で働きたい」という方におすすめの資格です。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務のキャリアをスタートするうえで、基本的な資格の取得は「やる気」と「基本スキル」を証明する手段になります。
未経験者が就職・転職の際にアピールできる材料になるため、最初の一歩としてとても効果的な資格といえます。
特定の分野に特化した医療事務資格
医療事務の中でも、レセプト作成や調剤報酬請求など、特定の分野に特化した資格があります。
以下のような資格は、業務経験者がスキルアップを目指す際や、特定業務に強みを持ちたい人におすすめです。
これらの資格は、純粋な医療事務資格ではないものの、「レセコンを使った請求」や「医薬品の販売」などの分野に特化しており、専門性を持って即戦力として活躍できる人材を目指せます。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
特化型資格は、現場で「この分野に詳しい人材」として高く評価されやすく、他者との差別化にもつながります。
スキルの深掘りをしたい方や、特定の職場(調剤薬局やレセプト専門部署など)で働きたい方にとって、強力な武器になります。
専門性の高い上級資格
医療事務としてある程度の経験を積んだ後、さらなるスキルアップやキャリアの幅を広げたい方におすすめなのが、以下のような上級資格です。
上級資格を取得することで、現場の実務から一歩踏み出し、組織の中核やマネジメントポジションを目指すことも可能になります。
長期的に医療業界や医薬品販売業界でキャリアを積みたい方にとって、将来性のある選択肢といえるでしょう。
医療事務のおすすめ資格9選
医療事務の資格は多岐にわたりますが、ここでは特に注目度が高く、キャリア形成に役立つ9つの資格を詳しく紹介します。それぞれの資格の特徴を理解し、自分に最適な資格を選択しましょう。
| 資格名 | 難易度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 医療事務検定試験 | 簡単 | 医療事務の入門資格 講座を通して体系的に学べる 転職を目指す未経験者におすすめ |
| 医師事務作業補助技能認定試験 | 簡単 | 医師をサポートする仕事 コミュニケーションスキルを活かして病院で働きたい人におすすめ |
| 登録販売者 | やや難しい | 将来の高い公的資格 第2類・第3類医薬品を販売可能 店舗管理者・責任者を目指せる |
| 医科医療事務管理士 | 簡単 | 医療事務スキルの客観的証明可能な資格 試験合格率は80%前後のため |
| 医事コンピュータ技能検定試験 | 簡単 | レセコンスキルを習得可能 医療事務とITスキルを同時に高められる |
| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | 簡単 | 50年以上の歴史ある資格試験 医療事務だけではなく接遇スキルも学べる |
| 医療事務技能認定試験 | 簡単 | 医療事務未経験者向け |
| 調剤事務管理士技能認定試験 | 簡単 | 薬に関わる仕事をしたい人におすすめ |
| 診療報酬請求事務能力認定試験 | やや難しい | 医療事務の中では難関資格 2026年3月31日に解散予定 |
医療事務検定試験
- 医療事務の入門的資格
- 難易度は低く取得しやすい
- これから医療事務の仕事に就きたい未経験者におすすめ
医療事務の講座申込はこちら!
医療事務検定試験は、医療事務の基礎を学ぶための入門的な資格として人気の高い検定試験です。
医療事務検定試験は「日本医療事務協会」が実施しており、医療事務の基本的な知識を幅広く評価します。未経験者でも取得しやすい資格として知られており、医療事務職を目指す方の第一歩として最適です。
医療事務の仕事は資格が必須ではありませんが、資格取得を通して医療保険制度や請求事務の基礎を学ぶことができるため、未経験者が転職する際には非常に役立つ資格といえるでしょう。
| 資格名 | 医療事務検定試験 |
|---|---|
| 受験資格 | 日本医療事務協会、および同協会の認定校の講座を修了 ※一般受験は別途問い合わせ |
| 合格率 | 90.6% ※2023年度の日本医療事務協会の講座修了者の合格率 |
| 学習時間の目安 | 3か月 ※日本医療事務協会の講座の標準学習時間 |
| 試験日程 | 毎月 第4日曜日 |
| 受験費用 | 7,700円(税込) |
| 主な就職先 | 病院やクリニックの受付および医療事務 |
| 公式HP | https://www.ijinet.com/ |
医療事務検定試験の取得方法
医療事務検定試験を受験するためには、基本的に日本医療事務協会(もしくは認定校)で開講している「医療事務講座」の通学コースまたは通信コースの受講が必要(※)となります。
講座では医療保険制度の基礎から実践的な医療費計算まで、段階的に学習を進めることができます。試験は自宅受験方式で、毎月第4日曜日に実施されています。
医療事務検定試験の難易度
医療事務検定試験は、数ある医療事務資格の中でも入門レベルに位置づけられており、講座受講生の合格率は90.6%(※)と非常に高い実績となっています。
試験は学科試験(正誤問題20問、記述問題5問)と、実技試験(会計欄作成)で構成され、総得点の70%程度を合格基準としています。
医療事務検定試験の資格取得がおすすめな人
医療事務検定試験は、「これから医療事務として働きたい」と考えている未経験の方におすすめの資格です。
講座を通じて、医療保険制度やカルテの読み方など、実務に役立つ基礎知識を動画教材やオリジナルテキストを使って学ぶことができます。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務検定試験に合格することで、実務経験がなくても「医療事務を体系的に学んだ証明」が出来るため、医療事務求人へ応募した際の説得力が高くなるでしょう。
また、資格取得の過程で、実際の業務でも役立つスキルが自然と身につく点も大きな魅力です。
比較的難易度が低い医療事務資格のため、未経験から医療業界を目指す方はまず最初に取得を検討するといいでしょう。
医療事務の講座申込はこちら!
医師事務作業補助技能認定試験
- 医師をサポートする仕事
- コミュニケーションスキルを活かして病院で働きたい人におすすめ
医師事務作業補助技能認定試験は、「医師事務作業補助職」振興のために創設された資格で、2009年3月から一般社団法人日本医療教育財団で実施されている資格試験です。
「医師事務作業補助体制加算」を得るために必要になる「32 時間以上の研修」において習得が必要な科目に対応しているため、安心して受講できます。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医師事務作業補助者は、医師の時間外労働を減らし、業務負担を軽減することを目的とした専門職で、今後ますますの活躍が期待されています。
また、適切な人員体制を整えることで、病院は「医師事務作業補助体制加算」を受けることができるため、医師のサポートだけでなく、病院経営の観点からも重要な役割を担う職種といえるでしょう。
| 資格名 | ドクターズクラーク |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 不明 |
| 学習時間の目安 | 不明 |
| 試験日程 | 毎月 |
| 受験費用 | 10,560円(税込) |
| 主な就職先 | 病院・クリニック |
| 公式HP | https://www.jme.or.jp/exam/dc/index.html |


医師事務作業補助技能認定試験の取得方法
医師事務作業補助技能認定試験は、年齢や経験を問わず、誰でも受験可能です。試験は毎月複数回実施されており、インターネット受験(IBT方式)によって、自宅でも安心して受験できます。
学科試験では、医療関連法規、医学一般、薬学知識、診療録、医師事務作業の基本など幅広い領域が出題され、実技では診断書・処方せんなどの医療文書作成能力が問われ、試験に合格することで「ドクターズクラーク」を名乗れるようになります。
医師事務作業補助技能認定試験の難易度
医師事務作業補助技能認定試験は決して難しくはなく、医療事務や医療知識に初めて触れる方でも対策をすれば合格可能な水準です。
合格率の公表はありませんが、以下のような合格基準が設けられています。
- 学科・実技ともに70%以上の得点
- 実技試験の各問で30%以上の得点が必要
出題範囲は非常に幅広いものの、参考資料の使用が許可されているため、暗記よりも「調べる力」「読解力」「文章の正確性」が問われる試験といえるでしょう。
医師事務作業補助技能認定試験の資格取得がおすすめな人
医師事務作業補助技能認定試験は、医師事務作業補助者として病院で働きたい人や、未経験から医療業界への転職を考えている方におすすめの資格です。
医師の働き方改革の開始に伴い、今後ますます負担を軽減する医師事務作業補助者のニーズが高まることが予想されるため、できるだけ早く資格を取得して働くことで、高い専門性を身につけることができるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
「医師事務作業補助者」は勤務医の負担を軽減することが主な役割です。
そのため、必然的に医師とのやり取りが増えるため、スピーディで的確なコミュニケーションスキルが求められる仕事といえるでしょう。
>医師事務作業補助者の資格はどれがいいのか?おすすめ資格を徹底解説




登録販売者
- 将来性の高い公的資格
- 第2類・第3類医薬品を販売できるようになる
- 経験を積むことで店舗管理者になることも可能
登録販売者は、2009年6月の薬事法改正によって誕生した公的資格です。
参照:e-GOV法令検索「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
登録販売者は、薬剤師に次ぐ「医薬品販売のプロ」として、一般用医薬品(第2類、第3類)の販売に携わることができます。これは医薬品全体の90%以上を占めており、ドラッグストアや薬局、コンビニ、スーパーなど幅広い場所で活躍できます。
| 資格名 | 登録販売者 |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 40~50% (東京都の2024年度試験の合格率:45.8%) |
| 学習時間の目安 | 300~400時間 |
| 試験日程 | 年1回 (実施日は都道府県によって異なる) |
| 受験費用 | 都道府県により異なる |
| 主な就職先 | 調剤薬局 ドラッグストア |
| 公式HP | https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/iyaku/tourokushiken |
>登録販売者におすすめの転職エージェント・転職サイトを徹底比較


登録販売者の取得方法
登録販売者になるには、以下のステップを踏む必要があります。
- 各都道府県が実施する「登録販売者試験」に合格すること
- 就職先を探す
- 販売従事登録(勤務地の都道府県)を行うこと
各都道府県が実施する試験に合格し、登録販売者として働くための就職先を決め、そのうえで都道府県知事の販売従事登録を受ける必要があります。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
一定の従事期間などの条件を満たすことで、研修中の立場から「正規の登録販売者」として認められ、管理者要件もクリアできるようになります。
これにより、ドラッグストアなどで店長や責任者として働く道が開けるため、収入アップを目指す方は、試験合格後できるだけ早く実務経験を積むようにしましょう。
>登録販売者が「食べていけない」「役に立たない」と言われる理由を解説


登録販売者の難易度
登録販売者試験の合格率は、おおむね40〜50%前後となっており、他の国家資格・公的資格と比べると簡単ですが、医療事務関連資格のなかでは最も難しい資格といえるでしょう。
| 試験年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2021年度 | 47.3% |
| 2023年度 | 47.4% |
| 2023年度 | 43.7% |
参照:厚生労働省「これまでの登録販売者試験実施状況等について」
登録販売者の資格は他医療事務資格に比べると専門性が高く、試験範囲が幅広いことから、決して簡単な試験ではありません。


登録販売者の資格取得がおすすめな人
登録販売者の資格は、「将来性の高い資格を取りたい人」や「資格を取ってキャリアアップしたい人」に特におすすめです。
また、実務経験を積んで「正規の登録販売者」になることで、店舗管理者などを目指すことも出来る資格のため、手に職をつけつつキャリアアップ・年収アップを目指しやすい資格といえるでしょう。
>登録販売者におすすめの転職エージェント・求人サイトはコチラ


医科医療事務管理士
- 医療事務スキルの客観的証明ができる資格
- 試験合格率は80%前後のため挑戦しやすい
- 体系的な知識を身につけたい人におすすめ
医科医療事務管理士は、医療保険制度や診療報酬請求に関する知識や実務能力を客観的に証明する資格です。
この資格は、技能認定振興協会(JSMA)が実施しており、在宅やインターネットでの受験が可能なため、気軽にチャレンジしやすいのが大きなメリットです。
また、医科医療事務管理士は病院やクリニックでの認知度も高く、資格を取得することで就職活動において有利に働くことが期待できます。
| 資格名 | 医科医療事務管理士 |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 80%前後 (※2025年2月試験の合格率:80.1%) |
| 学習時間の目安 | 300~400時間 |
| 試験日程 | 毎月 (※インターネット試験ならいつでも受験可能) |
| 受験費用 | 7,500円(税込み) |
| 主な就職先 | 病院やクリニックの受付 病棟クラーク レセプト業務 カルテ管理業務 |
| 公式HP | https://www.ginou.co.jp/qualifications/iryojimu.html |
医科医療事務管理士の取得方法
医科医療事務管理士の資格は、技能認定振興協会(JSMA)が実施する技能認定試験に合格することで取得できます。
在宅試験では、学科試験がマークシート形式10問、実技試験はレセプト点検1問とレセプト作成2問(外来・入院)で構成されています。
一方、インターネット試験では、学科50問・実技60問の択一式となっており、好きなタイミングで受験することができます。
合格基準は、在宅試験では学科・実技ともに80%以上、インターネット試験では総合で70%以上の得点が必要です。
医科医療事務管理士の難易度
医科医療事務管理士の難易度は決して高くありません。
| 試験回 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 80.8% |
| 2025年1月 | 82.3% |
| 2025年2月 | 80.1% |
参照:技能認定振興協会(JSMA)「試験実績」
また、万が一不合格になってしまった場合でも、2カ月に1回のペースで試験があるので、再挑戦もしやすい資格です。
医科医療事務管理士の試験範囲は、医療保険制度や公費負担医療制度といった法規、診療報酬点数の算定や診療報酬明細書(レセプト)の作成、医療用語などの保険請求事務に加えて、医学一般まで幅広い分野にわたります。
合格のためには、実際に多くのレセプトを作成し、実践的なスキルを身につけることが重要です。特に未経験の方は、技能認定振興協会(JSMA)の公式サイトで紹介されている試験対策教材や問題集を活用するとよいでしょう。
なお、在宅試験では、テキストやノート、電卓などの参考資料を使用することが可能です。
医科医療事務管理士の資格取得がおすすめな人
医科医療事務管理士の資格は、これから医療事務の仕事に転職したい未経験者はもちろん、知識を体系的に整理したい経験者にもおすすめです。
また、全国どこでも医療事務の仕事に就きやすくなるため、安定した職場を目指す方にとっても、非常に有効な資格といえるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
ただし、医療事務の業界では、資格よりも実務経験が重視される傾向があります。
そのため、就職を前提に資格取得を考えている場合は、まずハローワークや派遣会社などで、自分の希望に合った求人を事前にリサーチしておくとよいでしょう。
先に就職先のイメージを持っておくことで、資格選びにも無駄がなくなります。
医事コンピュータ技能検定試験
- レセコンスキルが身に付く資格
- 準1級~3級まであるのでレベルに合わせた挑戦が可能
- 医療事務とITスキルを同時に高めたい人におすすめ
医事コンピュータ技能検定試験は、一般社団法人医療秘書教育全国協議会が実施する試験で、医療事務に必要な知識だけでなく、コンピュータ操作や専用ソフト(通称「レセコン」)を使ったレセプト作成能力も問われます。
医療現場では、診察情報や会計処理を正確かつ迅速に行うために、医事コンピュータの活用が欠かせません。医事コンピュータ技能検定試験は、そうした現場ニーズに応える実践的なスキルを有するかどうかを測る検定です。
3級から準1級までの3段階が設けられ、いずれも「医療事務」「コンピュータ知識」「実技」の3領域から出題されます。
| 資格名 | 医事コンピュータ技能検定試験 (準1級・2級・3級) |
|---|---|
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 80%前後 |
| 学習時間の目安 | 30時間前後 (※講座受講時) |
| 試験日程 | 年2回 (2025年は6月・11月実施) |
| 受験費用 | 準1級:10,000円 2級:9,000円 3級:7,500円 ※個人受験の場合 |
| 主な就職先 | 病院やクリニックの受付 病棟・外来クラーク等 |
| 公式HP | https://www.medical-secretary.jp/iji/ |
医事コンピュータ技能検定試験の取得方法
医事コンピュータ技能検定は年2回(6月・11月)実施されており、全国の指定会場で受験できます。願書はWebまたは郵送で提出可能で、誰でも受験が可能です。
各級のレベルに応じて試験内容が変わりますが、いずれも以下の3領域から出題されます。
- 領域Ⅰ:医療事務
-
医療保険制度や診療報酬点数、患者負担金の仕組みなど。
- 領域Ⅱ:コンピュータ関連知識
-
電子カルテシステムの基本操作、および基本的なITスキル・セキュリティ対策など。
- 領域Ⅲ:実技(オペレーション)
-
レセコンを使ったレセプト作成や負担金・診療費の計算など。
医事コンピュータ技能検定試験の難易度
医事コンピュータ技能検定の難易度は、以下のように段階的に設定されています。
- 3級:基礎的な知識と操作スキルを有し、正しくレセプトが作成できるレベル
- 2級:より正確かつスピーディにレセプト作成をこなせる一般的な実務レベル
- 準1級:複雑な症例やDPC制度への対応も含め、実践力が求められる上級レベル
また、3級や2級であっても、3領域すべてにおいてまんべんなく知識とスキルを身につけておく必要があります。
領域Ⅰ~Ⅲ全て60%以上正解で合格。
医事コンピュータ技能検定試験の資格取得がおすすめな人
医事コンピュータ技能検定試験に合格することで、レセコン操作の基礎があることを証明できるため、医療事務員としての就職・転職を目指す人におすすめです。
医療現場では「資格より実務」と言われがちですが、採用担当者にとっては「業務への理解度や意欲の指標」として評価されるケースが多く、スキルの裏付けとして有効な資格です。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医事コンピュータ技能検定試験は、医療事務としての基礎力だけでなく、実務に即したスキルの証明として非常に有効な資格です。
実務未経験でも「レセコン操作ができる」という客観的なアピールができるため、医療機関での就職活動に強みを持てます。
これまでデスクワークの経験が無い人や、PCスキルに不安がある人は取得を前向きに検討するといいでしょう。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
- 50年以上の歴史ある資格
- 医療事務だけではなく接遇スキルも学べる
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、一般財団法人 日本医療教育財団が実施する、医療事務分野における最大規模の全国統一試験です。
医療機関で必要とされる診療報酬請求事務や窓口での患者接遇などの実務スキルをバランスよく審査するのが特徴で、合格者には「メディカルクラーク」の称号が付与されます。
その信頼と実績から、全国の病院・クリニック・訪問診療所などで高く評価されており、履歴書に記載することで就職や転職時の有力なアピールポイントになる資格といえるでしょう。
| 資格名 | メディカルクラーク |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 不明 |
| 学習時間の目安 | 不明 |
| 試験日程 | 毎月 |
| 受験費用 | 8,800円(税込) |
| 主な就職先 | 病院・クリニックの医療事務 |
| 公式HP | https://www.jme.or.jp/exam/mc/index.html |
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)の取得方法
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、年齢や経験を問わず誰でも受験可能です。試験は毎月複数回実施されており、全国どこからでもインターネット(IBT方式)で受験可能です。
試験は、学科試験と実技試験の2つに分かれて実施されます。終了後すぐに結果を画面上で確認でき、合格した方には合格証書が交付されます。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)の難易度
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)の取得難易度は高くなく、万が一不合格になってもすぐに再挑戦が出来るため、初心者でも取得しやすい資格といえるでしょう。
学科試験では医療事務知識について60問が出題され、実技試験では患者接遇、診療報酬明細書の作成、基本診療料および特掲診療料の計算、外来会計の点検・病名との突合などが課されます。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)の資格取得がおすすめな人
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、医療事務として転職を目指す未経験者や、信頼性・知名度の高い資格で履歴書の印象を強化したい方におすすめの資格です。
この試験は、病院団体や公益社団法人全日本病院協会と提携しており、資格を取得することで「即戦力」としての評価が高まり、未経験者でも就職のチャンスを広げることができるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)は、単なる医療事務の知識だけではなく、患者接遇や診療報酬請求といった実務スキルを重視した資格です。
そのため、資格を取得することで、未経験でも医療事務員として働ける可能性を高めることができるでしょう。
医療事務技能認定試験
- 医療事務の仕事が未経験の人向け
- できるだけ確実に医療事務の資格を取りたい人におすすめ
医療事務技能認定試験は、医療事務職に求められる基礎的な知識や診療報酬の算定ルールを理解しているかを評価する資格試験です。
技能認定振興協会(JSMA)が主催しており、試験は在宅またはインターネット形式で受験可能。医療機関の受付・会計・保険請求など、幅広い業務に対応できる人材であることを証明できる資格です。
診療報酬明細書(レセプト)作成の実技だけでなく、医療制度や法規などの基礎知識も問われるため、医療事務職への第一歩として非常に有用です。
| 資格名 | 医療事務技能認定試験 |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 90%前後 (※2025年2月試験の合格率:86.7%) |
| 学習時間の目安 | 不明 |
| 試験日程 | 毎月 (※インターネット試験ならいつでも受験可能) |
| 受験費用 | 5,000円(税込) |
| 主な就職先 | 病院やクリニックの医療事務員 |
| 公式HP | https://www.ginou.co.jp/qualifications/iryojimu_ginoushi.html |
医療事務技能認定試験の取得方法
医療事務技能認定試験は、年齢・学歴・医療事務の経験を問わず、誰でも受験することができます。
また、テキストやノートの持ち込みが認められているため、実務に近い感覚で受験できるのが特徴です。合格すれば資格が発行され、医療事務の基礎スキルを有していることを証明できます。
医療事務技能認定試験の難易度
医療事務技能認定試験は、医療事務に関する基礎を固めたい人や資格を取って転職に活かしたい人におすすめです。
以下表を見ると分かるように、直近の合格率は80~90%を推移しており、試験対策をしっかりすれば合格は難しくありません。
| 試験回 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 81.8% |
| 2025年1月 | 86.2% |
| 2025年2月 | 86.7% |
参照:技能認定振興協会(JSMA)「試験実績」
医療事務技能認定試験に合格するためには、医療保険制度や保険請求事務の基礎知識に加え、情報システムの基本的な理解が必要です。そのため、テキストや参考書を効率的に活用できるかがポイントとなります。
実践的な演習問題に繰り返し取り組むことで、無理なく合格を目指すことができます。合格後は、医療機関での実務や関連資格の取得によって、さらなるスキルアップが可能です。
医療事務技能認定試験の資格取得がおすすめな人
医療事務技能認定試験は、以下のような方に特におすすめです。
- 医療事務の基礎をしっかり学びたい未経験者
- 子育てや介護と両立しながら在宅で受験したい方
- ブランクからの復帰を目指す人や再就職希望者
- 将来的に医療事務管理士など上位資格を目指す人
医療事務技能認定試験は、医療事務が未経験の方や、医療保険制度やレセプト作成を体系的に学びたい方におすすめの資格です。
試験を通じて、医療事務員に求められる基本的な知識を習得できるだけでなく、在宅試験やインターネット試験(IBT)を選べるため、自宅にいながら自分のペースで受験できます。
特に、オンラインで完結できる点は、多忙な社会人や主婦層にとって大きなメリットです。時間や場所に縛られず、スキマ時間を活用して無理なく資格取得にチャレンジできます。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
医療事務技能認定試験の難易度は低めですが、医療事務の土台を証明する資格のため、就職活動時のアピール材料としても有効といえるでしょう。
調剤事務管理士技能認定試験
- 保険調剤薬局で活躍
- 薬に関わる仕事をしたい人におすすめ
調剤事務管理士技能認定試験は、技能認定振興協会(JSMA)が実施する試験で、保険調剤薬局での受付や会計、レセプト業務などを担当する事務スタッフのスキルを証明する資格試験です。
処方せんの内容をもとに調剤報酬を正確に計算するスキルは専門性が高く、一度身につければ全国どこでも働くことができます。
| 資格名 | 調剤事務管理士技能認定試験 |
|---|---|
| 受験資格 | 特に無し |
| 合格率 | 80%前後 (※2025年2月試験の合格率:70.6%) |
| 学習時間の目安 | 不明 |
| 試験日程 | 毎月 |
| 受験費用 | 6,500円(税込) |
| 主な就職先 | 病院の薬剤部 保険調剤薬局 |
| 公式HP | https://www.ginou.co.jp/qualifications/chozai-jimu.html |
調剤事務管理士技能認定試験の取得方法
調剤事務管理士技能認定試験は、年齢・学歴・経験を問わず誰でも受験可能です。
現在は「在宅試験」と「インターネット試験(IBT方式)」の2通りの受験スタイルが用意されており、自分の都合に合わせて選べるのが大きな魅力です。
インターネット試験試験の場合、受験後すぐに結果が分かるため、できるだけ早く結果が知りたい人におすすめの受験方法といえるでしょう。
調剤事務管理士技能認定試験の難易度
調剤事務管理士試験の合格率は約80%程度で、比較的簡単に取得できる資格といえるでしょう。
| 試験回 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 74.6% |
| 2025年1月 | 80.0% |
| 2025年2月 | 70.6% |
参照:技能認定振興協会(JSMA)「試験実績」
しっかりと対策すれば合格できる水準ですが、調剤報酬点数の理解や薬剤用語の知識など、専門的な内容が出題されるため、油断は禁物です。
とくに初学者の場合は、問題集や過去問を繰り返し解いて、処方せんやレセプトに慣れておくことがポイントとなります。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
テキストやノート等の資料、計算機の使用が可能ではあるものの、事前にしっかり対策をしておく必要があるでしょう。
調剤事務管理士技能認定試験の資格取得がおすすめな人
調剤事務管理士技能認定試験は、全国どこでも働ける「手に職」の資格として魅力がありますが、医療事務に比べて学習範囲が「調剤報酬の請求」や「調剤報酬点数の算定」などに特化しているため、初学者でも比較的取り組みやすく、合格を目指しやすいのが特徴です。
そのため、医療業界の中でも調剤薬局や病院の薬剤部などで働きたい人におすすめの資格です。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
地域によっては、「調剤薬局事務」の求人が少ない場合もあります。
転職を前提に資格取得を考えている場合は、まず希望する地域の求人状況を確認したうえで、資格取得を検討するとよいでしょう。
診療報酬請求事務能力認定試験
- 医療事務の中では難しい資格
- 2026年3月31日に解散予定
公益財団法人日本医療保険事務協会が主催する「診療報酬請求事務能力認定試験」は、医療事務の資格の中でも最も権威のある資格のひとつとして知られています。
医療保険制度やレセプト作成に関する深い知識と実務能力が求められる試験で、合格することで高度な専門性が評価されます。
参照:公益財団法人日本医療保険事務協会「試験事業の終了と当協会の解散について」
今後は試験制度がなくなりますが、「診療報酬請求事務能力認定試験」に合格していれば、医療事務における専門性の高さを十分に証明できます。受験を検討している方は、早めの申込みをおすすめします。
| 資格名 | 診療報酬請求事務能力認定試験 |
|---|---|
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 30%前後 (第1回~61回までの平均合格率:30.9%) |
| 学習時間の目安 | 400時間前後 |
| 試験日程 | 年2回実施(7月、12月) |
| 受験費用 | 9,000円(税込) |
| 主な就職先 | 病院やクリニック 専門学校の講師 |
| 公式HP | https://www.iryojimu.or.jp/ |
診療報酬請求事務能力認定試験の取得方法
診療報酬請求事務能力認定試験は医科と歯科に分かれており、それぞれ学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。
ただし、診療報酬請求事務能力認定試験は2025年度の試験が最後になるため、受験を検討している人は間に合うように申し込む必要があります。
診療報酬請求事務能力認定試験の難易度
診療報酬請求事務能力認定試験の合格には、医療保険制度の深い理解と、複雑な診療報酬計算の正確な知識が必要です。特に実技試験では、制限時間内での診療報酬請求書・診療報酬明細書作成スキルが求められます。
直近の合格率は30~40%前後となっており、多くの受験者が半年から1年程度の学習の上で試験に臨んでいるようです。
| 試験回 | 合格率 |
|---|---|
| 第59回 | 48.2% |
| 第60回 | 33.3% |
| 第61回 | 41.1% |
試験の実施内容は「診療報酬請求事務能力認定試験ガイドライン」に基づいており、専門的な知識と実務能力の両方が求められます。
診療報酬請求事務能力認定試験の資格取得がおすすめな人
診療報酬請求事務能力認定試験は、医療事務の実務経験がある人の中でも、「もっと給与を上げたい」「専門性を高めたい」と考えている方に特におすすめの資格です。
また、医療機関によっては、この資格の合格者に対して資格手当を支給しているケースもあり、待遇アップやより良い職場への転職を目指す方にも最適な資格といえるでしょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
ただし、現在は多くの病院で診療報酬請求業務のDX(デジタル化)が進んでおり、従来の紙レセプトで必要とされていた実務スキルは大幅に効率化されています。
そのため、医療機関によっては、診療報酬請求事務能力認定試験の合格レベルのスキルを持つ医療事務員を必ずしも求めていないケースもあります。
資格取得を検討する際は、自身のキャリア目標や勤務先のニーズに合った資格かどうかを、よく見極めることが大切です。
医療事務の資格取得時の注意点
医療事務の資格は、就職やキャリアアップに有利な武器になる一方で、「なんとなく」取得しようとすると、かえって時間やお金を無駄にしてしまうこともあります。
医療事務資格を取得する際の注意点は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
安易な独学は時間のムダになる
「テキストを買って自己流でやればいい」と独学で医療事務の資格を目指す方も少なくありませんが、医療保険制度や診療報酬など、専門的な知識が多く含まれるため、初学者にとっては独学が難しいケースが多いです。
特に、出題傾向に沿った対策や、点数計算、レセプト作成の実技などは、独学だと「正しい理解」ができているかの判断が難しいため、結果として時間だけがかかり、合格には届かないことも少なくありません。
そのため、自分の学習スタイルや理解度に応じて、通信講座やスクールの利用を検討するのが効率的な資格取得方法といえるでしょう。
期限を忘れずに申し込む
医療事務の資格取得を目指す際は、試験の申込期限に間に合うように注意が必要です。
試験日時に合わせて、申し込みおよび学習スケジュールを立てて準備するようにしましょう。
勉強と仕事の両立には計画性が重要
医療事務の資格取得を目指す人の多くは、すでに働いていたり、家事・育児との両立をしていたりする方です。そのため、時間の使い方が合否に直結します。
また、モチベーション維持のために「模擬試験日を設定する」「学習の進捗を見える化する」などの工夫も効果的です。
- 毎日の学習時間の確保
- 週単位での学習目標の設定
- 試験までの学習スケジュール作成
- 復習時間の確保
無理のない学習計画を立て、着実に実行することで、確実な資格取得につなげていきましょう。
医療事務の資格の選び方
医療事務の資格には国家資格が無く、様々な団体が民間資格を発行しているため「どれがいいか分からない」と迷ってしまう人も多いようです。
資格選びは、単に「有名だから」「簡単だから」ではなく、自分のキャリア目標やライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、後悔しないための資格選びのポイントを3つ紹介します。
目指すキャリアパスで選ぶ
医療事務の資格は、これまでの経歴や将来のキャリアプランによって最適な選択が変わってきます。
- これまで医療事務の経験が無い人:医療事務検定試験
- レセプト業務に強くなりたい人:診療報酬請求事務能力認定試験
- 手に職をつけて安定して働きたい人:登録販売者・医師事務作業補助技能認定試験
一般的な医療事務職を目指す場合は、医療事務検定試験が適しており、より専門的なレセプト業務を担当したい場合は、診療報酬請求事務能力認定試験がおすすめです。
自分が就きたいポジションや医療機関の規模に合わせて、求められるスキルを明確にし、それに適した資格を選びましょう。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
キャリアの計画や目標が明確な人は、資格取得後の行動にも迷いがなく、ぶれにくい傾向があります。
「資格を取ってから考える」のではなく、「資格を活かしてどこを目指すか」をあらかじめ考えておくことで、就職活動や面接の場でも効果的にアピールできるでしょう。
とはいえ、自分ひとりでキャリアの方向性を具体化するのは簡単ではありません。将来に迷いがある場合は、キャリアバディで専門家に相談することをおすすめします。
取得にかけられる時間と費用で選ぶ
医療事務の資格は、3ヶ月以内で取得できるものから、半年以上かかるものまでさまざまです。また、スクールや通信講座を利用する場合は、受講料が数万円~十万円前後にのぼることもあります。
学習期間の目安や費用を公開している講座も多いため、複数のスクールを比較検討するのが良いでしょう。
資格取得には、それぞれ必要な時間と費用が異なります。自分の状況に合わせて現実的な計画を立てることが重要です。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
資格取得は自身のキャリアを作る「自己投資」ですが、現実的な制約(時間・お金)を無視すると継続が難しくなるため、無理のない計画こそが成功の鍵です。
短期集中か、じっくり学ぶか、生活リズムに合わせた選択を心がけましょう。
就職サポート制度の有無で選ぶ
医療事務の資格を取っても、それを「活かせる場所がない」状態では意味がありません。
とくに未経験から医療業界を目指す人にとって、就職サポートのある講座や団体の試験を選ぶことは大きなアドバンテージになります。
医療事務資格の転職への活かし方
医療事務の資格を取得した後、「どのように転職活動に活かせばいいのか分からない」という声は少なくありません。
せっかく手に入れた知識とスキルや知識を無駄にしないためにも、転職先の選び方や活用方法を知ることが成功への第一歩です。ここでは、医療事務資格を転職に活かすための4つの具体的な方法をご紹介します。
資格を活かせる職場を選ぶ
医療事務資格を活かすには、まず「資格が求められる職場」を選ぶことが基本です。医療事務の主な就職先には以下のようなものがあります。
- 病院・医療機関(総合病院やクリニック等)
-
受付業務やレセプト請求、カルテ管理など。医療事務の資格を最も活かしやすい職場です。
- 健診センターや検診機関
-
事務手続きや予約管理に強い人材が重宝されます。
- 調剤薬局・ドラッグストア
-
登録販売者や調剤事務管理士技能認定試験を活かせる職場です。
中には未経験でも応募できる職場もありますが、資格を持っていること自体がスキルの証明になるため、書類選考や面接でも有利に働きます。
さらに取得した資格を活かせる職場を探すには、求人サイトで資格名をキーワードに検索するのが効果的です。そのうえで、表示された求人の中から条件に合うものを選ぶことで、自分が身につけたスキルや知識を活かせる職場に出会える可能性が高まります。
医療事務に強い人材派遣会社に登録する
医療事務は派遣社員として働く人が多い業界です。特に、一定規模以上の総合病院では、医療事務の部門全体を派遣会社が請け負っているケースも少なくありません。
そのため、医療事務分野や病院への派遣に特化した派遣会社に登録することで、取得した資格に見合った職場を紹介してもらえる可能性が高まります。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
派遣社員として勤務すると、時給は高くなるものの「基本的に賞与が無い」等のデメリットがあるため、こだわりが無ければ直接雇用の求人と並行して探すようにしましょう。
医療業界に特化した転職エージェントに相談する
正社員や長期雇用を目指す場合は、医療業界特化や医療事務に強い転職エージェントを活用するのが効果的です。一般的な転職サイトでは出会えない、非公開求人や内部事情に詳しい担当者のサポートが得られます。
- 面接対策や履歴書の添削をしてもらえる
- 医療機関の雰囲気や人間関係など内部情報を教えてもらえる
- 希望に沿った条件での交渉(給与・勤務時間など)も代行してくれる
とくにブランクがある方や、今よりも良い条件で働きたいと考えている方には、エージェントに相談することで、転職成功の可能性が高められるでしょう。
ただし、より良い選択肢を見極めるためにも、セカンドオピニオンのような感覚で2〜3社の転職エージェントに同時登録し、並行して求人を紹介してもらうのがおすすめです。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
一人での転職活動に不安がある方には、医療系転職エージェントの利用を強くおすすめします。
求人の選定だけでなく、面接でのアピール方法までサポートしてもらえるので、医療事務の仕事が初めての人でも安心です。
ハローワークで求人を探す
地方在住の方や、地元での就職を希望する方はハローワークの活用も有効です。
医療機関の求人は地域密着型で出されることが多く、転職エージェントや人材派遣会社では見つかりにくい「クリニック」「小規模な病院」の求人紹介も受けられる点が特徴です。
- 求人数が多く、無料で利用できる
- 職員に相談すれば、応募先に連絡を取ってもらえる
- 書類の添削や職業訓練も受けられる
ただし、医療業界に詳しい担当者に当たるかどうかは運次第の面もあるため、転職エージェントや人材派遣会社と並行して利用するのが理想です。
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
ハローワークは地元で医療事務の仕事を探す際に特にオススメの転職活動方法です。
ただし、求人の見極めや交渉は自分で行う必要があるため、事前に希望条件や質問事項を整理しておきましょう。
医療事務の資格に関するよくある質問
医療事務の資格について、よくある疑問点について解説していきます。
資格の有効期限はあるのか
医療事務の資格は基本的に有効期限が無いものが多いですが、資格の種類によって異なるため、必ずチェックしておきましょう。また、更新不要の資格であっても、診療報酬改定や制度変更に対応するため、継続的な学習が推奨されます。
ダブルワークで医療事務は可能か
医療事務は、パートタイムやアルバイトなど、柔軟な勤務形態が選べるため、ダブルワークは可能です。ただし、勤務先との契約条件や労働時間の制限には注意が必要です。
未経験でも転職は可能か
医療事務は未経験者の採用も多い職種で、資格を持っていれば転職は十分に可能です。特に、資格取得者は基礎知識があると評価され、未経験でも採用されるケースが多くあります。
医療事務の役立つ資格まとめ
医療事務の資格取得は、医療機関での就職や転職において大きな強みとなります。
資格は必須ではありませんが、専門的な知識を証明し、実務でも即戦力として活躍できる可能性を高めます。特に、医療事務検定試験や医科医療事務管理士などの資格は、業界での評価が高く、キャリアアップの重要なステップとなります。
医療事務は、医療機関になくてはならない職種であり、今後も需要が継続する分野です。資格取得を通じて専門性を高め、やりがいのあるキャリアを築いていきましょう。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
医療事務の資格は多種多様で、どれを取得すべきか迷うことが多いと思います。その際は、本記事を参考に、現在のキャリア状況や将来の目標を考慮して選びましょう。
また、本記事で紹介されている資格以外にも「医療経営士」「施設基準管理士」「医療情報技師」など、経営や高度な専門スキルに特化した資格も存在します。
このように、医療事務には幅広いキャリアの選択肢がありますので、ご自身の望むキャリアに沿って最適な資格を目指して下さい。
.jpg)
.jpg)
鶴喰キャリアコンサルタント事務所代表
【保有資格】
- キャリアコンサルタント
- キャリアカウンセラー(JCDA認定CDA)
- NLPプロフェッショナルコーチ
- 両立支援コーディネーター
- 診療情報管理士(DPCコース修了)
- 医療経営士2級
- 施設基準管理士 他
【経歴】
鶴喰キャリアコンサルタント事務所代表。
現役の病院事務長として、医療経営や人材育成、キャリア支援に携わる傍ら、医療業界に特化したキャリアコンサルタントとして幅広い支援活動を行う。
大学卒業後、福岡県済生会福岡総合病院に入職し、医療制度や診療報酬請求業務などの知識を習得。
その後、民間病院にて経営企画部や医事部の業務に従事。2016年からは医事部部署長として50名以上のマネジメントを担い、病院収益改善や施設基準管理業務に取り組む。
2022年より医療法人の法人本部事務長に就任し、法人全体の経営管理業務に従事。
2021年にキャリアコンサルタント資格を取得し、医療・介護・福祉・健康・栄養業界に関わる人材や企業を対象に、キャリア支援や研修を提供。特に20代〜30代の若手転職希望者へのコーチングやキャリアコンサルティングを得意とし、経営分析や健康経営推進、人材育成・組織開発にも尽力している。
2025年5月4日監修




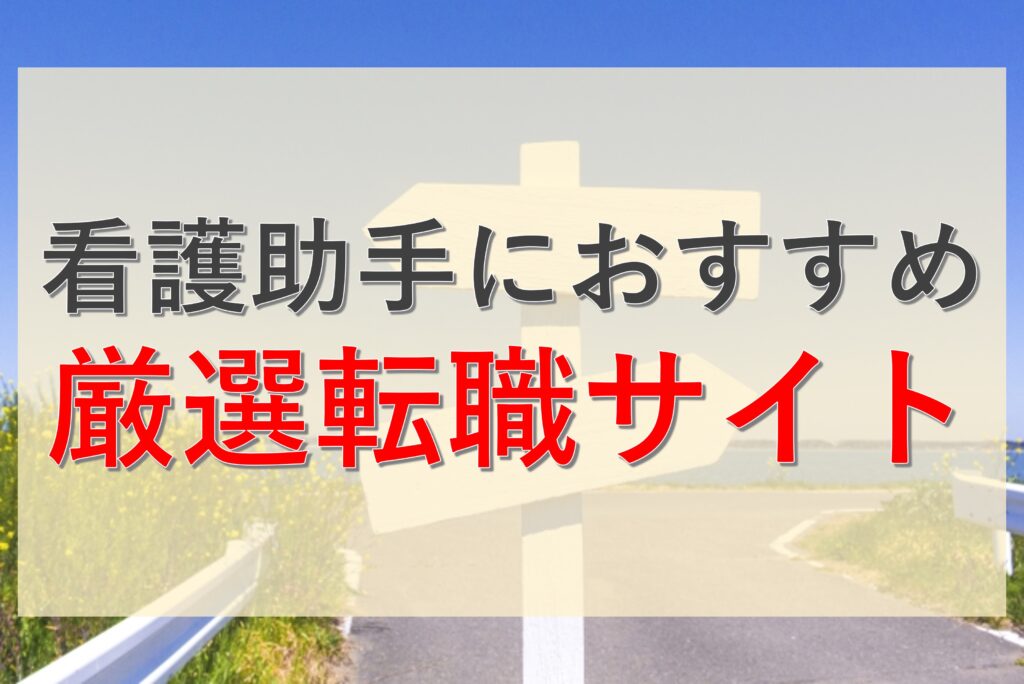
.png)






